ここに六冊の本がある。一九八九年発行の『絆』から始まって、『二枚の画布』『黒い花』『イブを見た女』『父の乳房』『詩集 小さな溶鉱炉』と毎年一冊のペースで発行してきた手作りの本である。
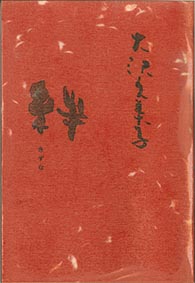 |
 |
 |
 |
 |
 |
私は勤めを持ちながら小説を書き続けていた。最初の頃は漠然とした作家志望という夢を抱いていた。それがやがて生きることがすべて書くことにつながってしまうようになった。書くことによって自分の生きざまを見つめ、人間社会のあり方を考え、辛いことや苦しいことに立ち向かうことが出来た。
「日本随筆家協会」「立像」「現代文藝」と書く人たちのグループに所属して、同人雑誌に作品を発表し続けた。それらの作品は「文学界」の同人雑誌評に何度か取り上げられ、今月のベスト5に選ばれたりもしたが、それだけのことでこれといって話題になるようなこともなく、作品は溜まっていく分、作家志望の夢は色あせていった。
食うために働くといった漠然とした生活に疲れれていた。何か自分の生涯をかけて出きることはないかと思うようになり、とりあえず一年に一冊自分の作品を本にするために働くのだという目標を立て生きてみようと考えた。
 |
 |
 |
「風の宿」「他人の城」「風の女」と日本随筆家協会から立て続けに出版した。それらはすべて私の父に表紙絵を描いてもらい、原稿を渡したら何ヵ月か経って本が出来上がってくるという他人任せのものだった。初めの一冊には感動があったが二冊三冊となると感動は薄れていった。二冊目の「他人の城」は、表題作が第十三回埼玉文学賞を受賞しており、出版記念会も経験した。テレビドラマ化の話があったと発行所から連絡を受けたがその後の経過は音沙汰無しだった。本は全国図書館選定図書にもなった。
その後、ワープロを使用するようになり、所属していた現代文藝研究所で発行していた文藝ジャーナルや同人誌、作品集などの印刷物を印刷所に出さずに研究所で作ることになり、出版部門を「現代文藝社」として、私はワープロで版下を作ることを手伝うようになった。
製版、印刷、製本の試行錯誤を繰り返す中で主宰者が、毎年発表した作品を一冊の本にしたいという私の意向を汲んで、研究所で出版したら自分の思い通りの本作りができると助言してくれた。
現代文藝研究所の事務所は、九畳ほどの狭い空間にコピー機や印刷機、帳合機、応接セット、冷蔵庫、本箱、ワープロ、主宰者の机や椅子など雑然と置かれて、より良い本作りのために何かしらの機器が毎年のように取り替えられ増えていき、その返済に主催者は四苦八苦していた。
事務所のベランダに向いた窓はいつも半分開けて、下の方に二〇センチ四方の穴があいた木の雨戸で塞いであった。その穴から主催者の飼い犬や近所の野良猫が出入り出来るようにしてあるのだ。犬や猫たちは好き勝手に出入して、印刷中のインクの中に足を突っ込んだり、帳合している印刷物の山を崩したり、とにかく本を作る環境には程遠いものだった。それでも主宰者は平然として、その邪魔者たちを追い出そうとはしなかった。
仕事が終ると酒盛りが始まる。電気コンロに鍋をのせ、仕事が始まる前から煮込んでいた煮物ができあがっている。缶ビールと焼酎を飲みながら鍋をつついて本作りの話に興じる。匂いを嗅ぎつけて、雨戸の穴からあるじの飼い犬や近所の野良猫たちが入って来て、スキあらばと酒のつまみを狙っていて、油断ならない事態になる。しかし、仕事を終えた充実感はほろ酔い気分の心も体も満たしてくれた。
できあがった本は、版面が不揃いで、ペラペラと捲るとページが踊っていたり、インクの濃さがページによってばらついていたり、同じページ内での印刷むらがあったりとなかなか思うようにはならなかった。表紙についてもハードカバーをどのようにするか、紙質をどうするか、製本の綴じ方など、難問が次から次と立ち塞がった。
二百頁を百部ほど手作業でやる帳合は、辛抱のいる作業で、いくら自分の本と思っても苦痛であった。なぜかといえば、ページの組み違いが不安なのである。何回も見直しを繰り返すことになるのだけれど不安が解消されるどころか、見直せば見直すほど新たな不安がつのってくる。できあがった本までもページの点検をすることになってしまうのだった。これに懲りて帳合機を購入したが、この不安は解消されなかった。
これでは他人の本を手作りして、渡してしまったあとまでも不安をひきずることになってしまうのではないか。そう考えると代金の請求などとてもできないことだった。これが六冊の手作りの本作りを体験しての実感だった。
それでも自分を含めて物を書く人の立場に立って考えて見ると、どうにかして作品を本にしたいという思いは切実で、その思いに何とか応えたいと願う主宰者の気持ちが、自費出版の仕事を手がけることに踏み切らせた。
出版がなぜ高いのか、手の届く価格はどれぐらいなのか、どうしたら安くて良い本が出きるかなど、私は主宰者とともに自費出版を手がけるにあたって、書き手の思いが反映される自費出版とはどういうことなのかいろいろ考えさせられた。
人は雇わない。印刷、製本は外注に出すが、できるだけ良い本作りを理解してくれる安い所を探す。表紙を一色刷りで見栄えの良いものはできないか。宣伝は公募ガイド一本にする。販売のルートは持たないことをはじめから明確にして、著者の必要部数のみつくる。料金表を提示する。
筆者の立場に立てば、自分の作品がより多くの人に読んでもらえることが出版の目的でもある。しかし、この要望に応えることは、今日の出版事情から考えても難しい。売れない本を承知で何千部もこしらえて、結局処分せざるを得ないのだったら、無駄な経費は省く方法を取る。
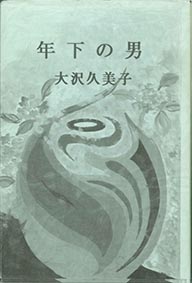 前記したようにはじめから販売はしない、売るための宣伝もしない、ということを明記して経費をかけない分、出版費用の軽減をする結論を出した。そのかわり、研究所で発行している文藝ジャーナルや研究生募集広告を活用して、本の発行をささやかではあるが世に知らせることにした。
前記したようにはじめから販売はしない、売るための宣伝もしない、ということを明記して経費をかけない分、出版費用の軽減をする結論を出した。そのかわり、研究所で発行している文藝ジャーナルや研究生募集広告を活用して、本の発行をささやかではあるが世に知らせることにした。
ようやく先の見通しが立ち、計画が少しずつ具体的になって、何冊かの本を作り軌道に乗り始め、現代文藝研究所の出版部門だった「現代文藝社」は、私に任されることになり独立した。
それから一年が経過して、 現代文藝研究所の所長であり、同人誌「現代文藝」の主宰者でもあり、一九八〇年から文学の指導を受けていた恩師田端  信先生は、癌で亡くなった。 その間に私は自分の祖父をモデルにした四百字詰め原稿用紙三百枚の小説「葦の原の夢」を出版に向けて推敲している段階だった。
信先生は、癌で亡くなった。 その間に私は自分の祖父をモデルにした四百字詰め原稿用紙三百枚の小説「葦の原の夢」を出版に向けて推敲している段階だった。
田畑先生は病院のベッドで死の病と戦いながら、最後までこの小説のことを気にかけてくれていた。
「これを書き上げたら次のステップだ」
師はまるで、じきに退院して次の作品の指導を楽しみにしているような口振りなのであった。 あれから四年の歳月が経とうとしている。手作りの六冊の本が生まれた部屋は今はない。しかし、あの狭い事務所で師と暴れ回る犬や猫たちと共に本作りをしたその志は、「現代文藝社」として今も私の中に受け継がれている。(自費出版ジャーナルに掲載)

