小さな文学館
私と癌
(38)
田 端 信
創設から十年ほどは、すべて印刷、製本屋の下請に出していた。印刷屋のスケジュールに合せて、こちらのスケジュールをたてる。ところが期日までに原稿や校正が間に合わないと、納期が大きくズレこんだ。それ専門の担当者がいるならともかく、色々な仕事を一人で調整しながらやる場合、大変なことだった。
そして、印刷屋へ行って見ていると、そう難しい仕事のようにも思えない。そこで自分でやってみようと思い立ったのである。今度の裁判で弁護士を頼まなかったのもそうだが、何でも自分でやって見ようとする性格が、ここでも頭をのぞかせたのである。早速、メーカーに電話して、デジタル印刷機を設備したのである。それをきっかけとして調子のいい営業マンの口車に乗せられて丁合機、製本機、断裁機、紙折機、、イマジオ、パソコンまで設備する羽目になってしまった。
ところが実際、印刷を始めてみてわかったことは、理想と現実の大きな喰いちがいだった。デジタル印刷機と名称はもっともらしいが、昔の謄写印刷機の自動化したものである。裏写りがひどくて、表裏共印刷する場合、一面の汚れとなって現れる。作品のタイトルや末尾の空白部分、太字、カットの図柄、表紙製版などでは特に著しかった。紙圧、印刷速度、インクの種類など工夫してみたがそれほど差異は認められなかった。でき上がったものは全く印刷物とはいえない代物である。
そこで検品として、どの程度のものまで通すかが問題だ。箸にも棒にもかからないものはその時点で廃棄するが、合格としたものも前頁の印刷が仕上がってから点検すると、その大部分を落さねばならない状態だった。また初めからやり直しである。しかし刷り直して、前より却って悪くなる場合も多い。それを繰り返しているうちに、不良品の山を築き、使用できる印刷物は数えるほどしかない状態だった。
また印刷もれによって白紙の出てくるものも大きな問題だった。吹紙口側の紙の一端が折れこんでいたり、シワがあったり、湿った紙、紙間に空気が浸透せず密着している場合など、紙圧に瞬間的な変化が起きて、二、三枚の紙が重なったまま飛び出す。その分が印刷されず、白紙になるのだ。
高度の印刷機にそんな現象は発生せず、多少レベルが落ちる印刷機でも重送抑止装置というものがついていて、その時点で取り除くことができる。ところが安物の印刷機にそんなものはついておらず、何枚裏白が出ようとたれ流しである。
この発見法がまた厄介だ。表裏の印刷終了ごとに点検、断裁前に点検、丁合機にかける前に点検、製本機にかける前に一枚ずつめくりながら丹念に点検する。もう出る筈がないのに、製本後も出てくる場合がある。その一頁のために破棄しなければならない。どうしてそうなるのか、信じられない気持である。
しかし、自分では不思議だが、それはなるべくしてなったのだ。初歩的ミスによる場合も少なくない。チェックしているのだが、ある頁は二回印刷し、ある頁は欠落している。表と裏の天地が逆になっている場合もある。表を印刷し裏を印刷する場合、逆さまにして給紙台におかねばならないのだが、普通に入れてしまったのである。あるいは一枚だけ試刷してそれを置くと、下もそうなっていると思いこみ、こんなミスが発生する。
製本後も裏白だけではなく、色々なミスが発生する。表紙と内容が逆になっている場合がある。これは表紙を製本台へ乗せるとき、一枚だけ逆になっていたのである。本文だけに気をとられているから、ミスには気がつかない。
本文の一部だけ天地が逆になっている場合、左右が逆になっている場合がある。
丁合機によって五十頁ぐらいずつ組み合せ、最後になってからそれを手によって組み合せる。頁を確認しながらの作業であるが、脳ミソが腐っていたとしか考えられないのである。一部の頁でハシラ(タイトル)、頁の欠落する場合があった。製版の直前に行数の動く訂正が発生したとき、その頁を打ち直すことがある。最後になってハシラ、頁を入れねばならないのに見落したのである。
ミスは至るところにある。編集者はよく、コウセイオソルベシというが、印刷、製本こそ恐るべしである。校正のミスは行間にあるが、印刷、製本のミスは空間にあるからだ。著名雑誌が三十全頁もけっらくしたまま店頭に並んだというが、それを物語っているのかもしれない。
ジャスミン茶の匂い
── 四十路半ば・春・香港&マカオ ──
新納三郎 作
読後感など下記までお寄せください。
〒340-0154埼玉県幸手市栄4-3-504
TEL0480-43-5599
新納三郎宛
1
香港の九竜地区を専用の観光バスで走っていると、あけた窓から一種独得の柔らかい匂い、日本では嗅いだことのない匂いが流れてきた。かすかな匂いだが、何やら甘く怪しく、危険で、執拗な感じがこもっていた。
飛行機による海外旅行につきものの時差や環境の急変で、まだ多少の混乱と疲労が抜け切らない僕の頭にも、その匂いをどこかで嗅いだ記憶が甦った。しかし、どこで嗅いだのか、どうしても思い出せない。
バスは、九竜のごみごみした繁華街の人波をかき分けるようにして走っている。中国の盛り場の匂い、中国人の生活の匂い、つまり、これが香港の匂いというわけだろう、と僕は思った。風向きのせいか、匂いはやがてふっと消えた。
「いま何か匂わなかった?」
僕は、飛行機の中で知り合ったパック・ツアーの同行者に尋ねた。
「ジャスミン茶の匂いよ」と彼女は答えた。
ああ、と僕は苦笑する。その朝もホテルでジャスミン茶を飲んできた、というより無理に喉に流し込んできたばかりではないか。前夜遅く着いた香港ヒルトン・ホテル十一階の僕の部屋のサイド・テーブルにあったのも、水ではなくて、保温のためだろう、厚い布カバーを被せた中国式(?)ポットに納まったジャスミン茶であった。
不覚にも僕は、それまで日本でジャスミン茶というものを飲んだことがなかった。
前日―—三月十九日午後十一時過ぎ、予定より二時間近くも遅れて、僕ら香港・マカオ・ツアー一行の便乗するパンナム001便は、軽い興奮のざわめきに包まれ、啓 徳空港をめざして高度を下げ始めた。単独参加の僕だが、香港・マカオは初めてである。いや、まだ中国大陸にも台湾にも行ったことがないから、その意味では初めての中国への旅であった。それもさる企業の招待旅行だから、半ば偶然の旅というべきで、僕は欠員補充という形で、一般募集のパック・ツアーグループに編入されたのだった。
夜が遅過ぎたせいか、座席の位置のせいか、飛行機から例の〝百万ドルの夜景〟はほとんど見えなかった。僕のほうも、久し振りに日本を離れるというのに、心は妙に弾まなかったし、また、これも単独参加で静岡からきたという隣席の、若いチャーミングな同行者に気をとられてもいたので、有名な夜景など、どうでもいいという気分だった。
「サングラスがとてもお似合いだわ」と、いわゆる団塊の世代らしい同行者が言った。
「ガードは大丈夫だから、万一の時の通訳は頼んだよ」
英語を喋れない僕は、大学の英文科出だという同行者に、お世辞半分で念を押した。
「自信ないわ。でも、中国人の話す英語なら却って聞きとりやすいかも、ね」
同行者は、屈託なげにケラケラ笑った。袖触り合うも多生の縁を願った僕に、同行者のほうからガードを頼んできたのである。サングラスを見込んで頼んできたのかも知れないけれど、顔をやさしく見せるため、いやむしろ、やさしくなるために掛けたのだから、似合わなくても困るが、似合っても何やら困る僕のサングラス。
それにしても久し振りの外国、初めての香港・マカオ、そして若いパートナーとせっかくペアを組みながら、僕の心が弾み切れないのは、四十五歳という齢にもよるだろうが、実をいうと、トゲのようなひっかかりも心底にあったからだ。
意識するなと言われても、やはり僕らの世代では、侵略戦争の過去を(たぶん必要以上に)意識してしまう。敗戦時、中学一年だった僕に〝戦争責任〟はないはずだが、それは国内だけで通用する話で、日本に侵略された傷痕を持つ外国へ行けば、少なくとも僕の意識の中では年齢の〝免罪符〟がさほど役立たないことを、ずっと以前の、といっても昭和三十年代半ばの短い外国生活でも思い知らされていた。
いや、外国へ行くまでもない——結局は卒業を果たせなかった学生時代、半ばアルバイト、半ばは革命をめざし“プチブル根性の克服„などという、今から思えば笑止千万な若い気負いでつづけた日雇い労働の日々、ともに働く在日朝鮮人たちとの交流の中でも、そのことを思い知らされたのである。ましてや中国に対し、日本人は最大の被害を与えている。しかも戦後処理を誤まったばかりでなく、いわゆる南京虐殺や侵略そのものさえ否定する日本人がいて、中国や韓国からの非難もやむことがないではないか。
僕の父も下士官として日中戦争に従軍し、金鵄勲章をもらった。あの〝大虐殺〟で知られる南京占領などから南転して、香港に近いバイアス湾上陸と広東(広州)占領、さらにトンキン湾上陸と南寧占領にも参加している。最前線で戦う下士官や兵が、軍人最高の栄誉だったという金鵄勲章を、戦死によってではなく日本に生還しながらもらうことの意味を、僕は戦後になって推量したものだ。父は一体、何人の中国兵、中国人を殺したのだろうか、と……。
たしか敗戦の翌年、僕は、戦地で撮った父の従軍スナップを何枚もアルバムから引き剥がし、破り捨てたことを憶えている。怒った父は僕を殴りつけたが、母は「戦犯で掴まるのを心配して破ったに違いなか」と僕を弁護してくれた。今から思えば、愚かなことをしたものだし、むしろ反面教師として、その種の写真は残しておくべきだったと悔いるのだが、当時の僕は、生活の大黒柱である父が戦争犯罪人で掴まることを恐れたからというより、ただもう破り捨てずにはおれない何やら激しい衝動に駆られて、そうしたのだった。
戦後の素朴な反戦平和・民主主義教育の影響、少年期の純粋さ、あるいは生来の軽佻浮薄さ、口やかましく厳格に過ぎた父への反抗期的反撥——それらの理由を合わせても、僕は、その時の自分の行為を充分に納得することができない。それは戦争で父が犯したに違いない罪悪を、単純に恥じた上での行為でもなかった。そういう言い方をすれば、戦後の僕は〝恥〟という感覚にきわめて鈍感になっていた。
やや皮肉な成り行きだが、その後、何らかの原因で精神が挫折するたび、過去の写真をすべて破り捨てるという僕の(青春期の誰にでもありがちな)いわばセレモニー的・自己罰的な補償癖も、父の従軍スナップを破棄した時を嚆矢とする。類推すれば、従軍スナップを破棄したことで、僕は父と旧日本ばかりでなく、〝軍国主義少年〟という過去の自分を罰したつもりだったのかも知れぬ。
そして、同時にあの戦争責任を国民にもアジア諸国にも取らない〝恥知らず〟な日本のリーダーたちと同様、〝過去からの逃亡〟を願う意識も働いていたはずである。写真と一緒に破り捨てるべきものの集積が、もはやセレモニー的補償行為などでは手に負えないほど大きくなった、と感じ出した青年期以降、僕のほんとうの逃亡が始まった。故郷からの逃亡、日本からの逃亡、家族からの逃亡、つまりは自分自身からの逃亡……。
日中戦争の〝手柄話〟を戦時中も戦後も、ただの一度も家族や僕にしたことがない父を、僕はひそかに尊敬していた。が、逆コースの半ばの定着に勢いづいてか、老いの心の弱まりか、それとも酒に酔い過ぎたのか、帰省時に同伴した僕の妻に金鵄勲章を出して見せ、よもやと思った古い戦 さの手柄話をくどくど語り始めた父の姿に、僕はがっかりしたものだ。
戦後生まれの妻は、そんな父のことを蔭で「ひどい脳軟化症。すぐ入院させなければ」と評したので、僕は二重にがっかりする羽目となる。「脳軟化症」は妻の皮肉でも、家族と引き裂かれ、三年近くも侵略戦争に駆り出されて、運よく生還したものの、青雲の人生設計が狂ってしまった父の半面の憐れへの若干の理解を、戦無派の妻にも望んでいたのだけれど。
旅の心が弾まない今一つの理由、先の児戯にひとしい写真破棄癖とも関連する、というよりは僕の〝本性〟とも関連する理由もあった。
罪が生起するのは戦争だけに限らず、一般的には戦争はむしろ特殊なケースに過ぎない。すなわち現実の生活で、多かれ少なかれ人は他者を傷つけずには生き得ないが、それにしても僕は、肉親同胞を含むあまりにも多くの他者を傷つけ過ぎてきた。なお僕に震撼を残すその二度目の妻子とも別れたのは二年前だが、すでに父のそれにもまさるあらわな鬼相を覆い隠すため、下請けながら仕事の独立自営を機に僕はこの十年来、視線の行方どころか目の所在すら定かでないほどの度つきサングラスを、顔から外せないテイタラクとなっている。
加えて、その鬼相の最初の明瞭な発現の時としか言いようのない二十代の半ば、大仰にいえば僕は自分にも日本にも絶望し、再生の希望に燃えつつ外国へ逃れたが、その希望もかなわぬ生殺しのまま、わずか四ヵ月で日本に追い返された無念の記憶も、以後ひたすら不徳の馬齢を重ね、疲れはて、鬼相のみが深まる二十年の歳月の中を生きつづけ、かつての外国逃亡と旅の性格は全く異なるとはいえ、ともかく外国・香港をめざす僕の心の弾みを妨げたかのごとくであった。
別れた子供たちの顔が目先にちらついて離れないのでは、心の弾みようもないのである。
2
熱帯圏に属する香港だけに、三月でもさすがに暖い。年甲斐もなくジーパンにTシャツ、サマージャンパーという軽装でも汗ばむくらいだった。
通関に時間をとられ、バスでホテルに着いた時、もう午前零時を回っていた。機内でブロンドのスチュワーデスがサービスするスコッチを飲み過ぎたせいか、喉が乾いた僕の目にすぐとまったのが中国風のポットと湯呑みというわけだった。てっきり普通のお茶だと思い、それでも用心して口に含むと、変な味がした。中国茶には違いないが、その味と匂いは僕の、いわば食文化的警戒心を呼びさますに充分な異文化の気配を漂わせていた。甘く怪しく、危険で、執拗な気配を……。
しかし、喉の乾きはどうにもならない。添乗員から「生水は飲むな」とのきついお達しもあり、冷蔵庫にはジュースやアルコール類ばかり、それに夜半ボーイに湯ざましを注文するのも面倒なので、我慢して飲んだ。招待客の僕だけ一人一室、訊く相手もいない。
食文化の国際化が進んでいるとはいえ、人間は本来、飲食物に対してきわめて保守的といわれる。現に旅慣れた同行者たちの中には、インスタント・パックのミソ汁や日本茶を持参する者もいた。翌日、大食堂でのバイキング形式の朝食の時、初めてその名を知ったのだが、やはり食卓にはジャスミン茶しか置かれていなかった。やむなく僕は、脂っこい中国料理をジャスミン茶で胃に流し込んだ。味覚保守の僕は、ジャスミンの花や香りのイメージに反して、ジャスミン茶にはどうしても馴染めないのだった。
けれども、観光バスの窓から流れてきたあのジャスミン茶の匂いは、なぜかそれほど不快ではなかった。舌や喉ではなく、鼻だけで感じたせいかも知れぬ。そういえば、と僕は車内の前方に佇む通訳兼ガイドの中年の中国人女性に目をやった。簡素なツーピース姿で、言葉遣いもアクセントも日本人と全く変わらないほどの語学力と、どこか翳りを含んだ小柄な笑顔が、最初から僕らの注意を惹いたのだが、彼女も同じジャスミン茶の匂いを漂わせていたことを、僕は思い出していた。
朝一番に訪ねたタイガーバーム・ガーデンを見て外へ出た僕と同行者のすぐ傍で、たまたま小雨を避けて軒先に立っていた彼女と視線が合い、互いに何となくほほ笑んで、日本に行ったことがないというのに、どこで、どうしてそんなに上手な日本語を学んだのかなどと、訊かずもがなの詮索をつづけている時、これまた風の加減か、僕の鼻をかすめた彼女の匂いがジャスミン茶の匂いだったのである。彼女は私事については言葉を濁し、ほとんど語らなかった。
「彼女にはどこかもう一歩、人を踏み込ませない壁があるわ」
去って行く中国人女性ガイドの後姿を見送りながら、同行者がささやいた。
「職業柄、客に一定の距離を保つ必要があるのだろう」と答えたものの、僕も内心、同行者の感想に同意していた。
「それとも、僕と同じぐらいの年格好だから、日本軍の香港占領で何か嫌な目に遭ったのかな……」
「大陸から逃げてきたのかも知れないわ。ベトナムのボート・ピープルもいるそうだけど、ここの住民の大部分が大陸からの難民か、その子孫でしょ?」
「つまり、香港は逃れの町というわけだ」
僕は、旧約聖書に出てくる〝逃れの町〟を何となく意識しながら、また、若い頃の〝逃れの町〟をめざした海外逃亡の記憶も重ね合わせながら、そう言ったのだった。
まさに若さのせいだろう———左右・中庸を問わず日本社会の〝出る杭は打たれる〟どころか、人がわずかに異質を持つだけで〝出ない杭〟さえも打たれるムラ社会文化、物蔭からの中傷と足の引っぱり合いの陰湿矮小な文化風土につくずく愛想をつかし、左翼崩れなどにはろくな働き口もない高度成長前の生活苦にも嫌気がさして……
さらにはわが身の不徳———失った実質的な最初の〝妻〟、今となっては唯一だったことを思い知る〝妻〃との愛と、その愛に背く、いやもしかしたらその愛に似合いの、まるで必殺の相打ち技のように互いにえぐり、えぐられた傷の深さの苦しまぎれに、文字通りの〝逃れの町〟に擬した外国ソ連へ逃れ出た二十六歳の頃のことを、僕は思い出していた。
そして、これも若さの余慶というべきか、少なくとも〝逃れの町〟での再生と自由と開放をめざす僕の心は、不安と隣り合わせながら、逃亡の船中でも逃亡先のソ連でも、弾みに弾んでいた。 愛するニノチカと出会ったのだから、なおさらではないか。
当時は、現在のように自由に海外へ行ける時代ではなかったので、商社の嘱託通訳として渡航し、機を見て現地退職、その首都の大学で学びたいという身勝手な青写真の〝海外逃亡〟も、当の商社におけるムラ社会的人間関係と、それに反撥する僕のエゴの衝突によって、たちまち終止符を打たれる結果となるのだけれど、日本に追い返された後も、北海道・知床から密航を図るなど悪あがきをつづけた挙句、経済生活も破綻して、結局〝海外再逃亡〟をあきらめざるを得なかった。
たしかに〝逃れの町〟への逃亡は、明日の幸せを賭けた跳躍でもあるにせよ、体は逃れても、心は罪や文化や自分自身から逃れ得ないことの意味の重さに、背を向けられるほど当時の僕はまだ若く、認識不足でもあったのだが、それだけになおさら、近くは日中戦争や内戦や共産革命、そして文化大革命などから〝逃れの町〟香港に——それも絶えざる不安と隣り合わせの香港に、再生と自由と開放を求めて逃れ出ることに成功した難民たち、つまりは現在の香港市民たちのありようが、何やら急に気になり始めたのだった。
仕事中は日本のガイドなみに能弁な働き者で、サービスも行きとどいた中国人女性ガイドに対し、早くも、いわばジャスミン茶的異和感を感ずるようなできごとが、一種のハプニングとして起こったのは、その九竜地区を走るバスにおいてである。彼女に対してというより、彼女というフィルターにちらりと映った香港や中国の文化の一端に対して、というべきかも知れぬ。
「いま町に出勤しているスリを見つけますから、皆さんも充分に気をつけて……」
初対面以来、スリへの注意を何度も僕らに喚起している彼女が真顔でそう言った時、僕らは好奇心を刺激されながらも、思わず笑い出したものだ。香港にはスリが多いというが、それにしても獲物を捜しに「町に出勤している」スリたち、しかも彼女に顔を知られたスリたちの中の誰かを、走るバスの中から簡単に見つけ出せるほど、それほどスリが多いというのか。
もし、彼女の言葉が、〝スリルとサスペンス〟で外国人をエキサイトさせる観光的でっち上げ、例えば窓外の無関係の通行人を「スリ」と言い立てるでっち上げではないとするなら、たしかに香港にはスリが多いにちがいない、と僕も当初はそう思った。ガイドの合い間、歩道の通行人に素早い視線を走らせていた彼女は、ものの五分と経たないうちに、声をことさらに低め、僕らにこう告げたのだから……
「ほら、交差点を渡っているあの男、白い開襟シャツの痩せた男がスリですよ」
指示された方角を見ると、それらしい白い開襟シャツの貧相な小男が何食わぬ、というか何の変哲もない顔つきで歩いていた。バスは、歩道に移ったスリと並ぶ格好で、しばらく徐行する。中国人運転手も心得たもので、被害にあわぬようスリの顔をよく見ておけというわけだろう。
車内は一瞬静かになったが、僕には女性ガイドの表情や声の響きのどこかに同国人を外国人の前で平気で「スリ」と暴露する〝個人主義〟にもまして、暴露してもなおある種の連帯を失わないような、スリに対する隠微な仲間意識が感じられ、またそれを通して、スリ集団にも暗黙裡に、いやおそらくは半公然と一定の〝市民権〟を認めているにちがいない香港社会の、いうなれば中国流の清濁併せ呑む文化的生命力の息遣いのごときものが感じられた。
東洋のカスバといわれた〝公認魔窟〟九竜城の存在を想起しても、僕の推察は当たらずといえども遠からずだろうし、スリはまさに本物でも、最大のカモであるはずの外国人観光団体客向けの彼の〝歩行〟は、当の外国人目当てのスリ行為に手ごころを加える、あるいは自粛するという条件でホテルや免税店、旅行会社、ガイド組合などからスリ集団に渡ったギャラのいくばくかを貰っての、連帯的・共済的な演出だろう、と僕は思った。
またそうでなければ、いくら密室的な外国人専用観光バスの中での暴露でも、いつかはそれがスリ集団にも洩れて、中国人が重視する面子も生活権も丸潰れとなり、地下社会の安定も乱されてしまうではないか。
とするなら、あの小男のスリはむろん顔を知られた〝大物〟などではなく、食うや食わずの腕の悪いスリ、ということになるのかも知れぬ。それとも、彼の肝心の指先に障害でも起きたのか。いずれにせよ僕には、外国人観光バスの走行ルートに沿って、大いなる屈辱と悲哀と諦観を胸に毎日ただ黙々と歩きつづけ、「スリ!」という何百人もの外国人の好奇の一瞥で生計を立てているにちがいない彼が、何やら魯迅の愛した〝阿Q〟のようにも見えてきたのだった。
僕が以上の推察を話すと、
「気の毒だわ。でも、すぐ国へ帰ってしまう外国人にだけ顔を知られたスリなんて、少し滑稽だけど、恥ずかしくないのかしら? 感覚がどこか日本人とちがうみたい」と同行者は笑って肩をすくめた。
「ちがうね」と僕も笑った。
とはいうものの敗戦直後の中学生時代、僕もあのスリのように何食わぬ顔をして、故郷の町を歩いていたのだろうか。僕は、自分が犯した古い悪事のことを思い出していた。結果的には、それが僕の故郷喪失と〝逃れの町〟願望の最初にして直接の動機となっただけに、忘れようにも忘れられない事件である。
いわば目糞と鼻糞の差に過ぎないけれど、僕はスリではなく万引き少年だった。近所の悪童連を集めて万引き団を作り、本や食べものなどを万引きして回った。近所の二軒の古本屋では、一軒で盗み他の一軒へすぐ売り飛ばすという悪辣さ。人口一万余の小さな町での悪事は当然やがて露顕したものの、僕の両親に遠慮するムラ社会的〝恩寵〟から、両親にも学校にも警察にも通報されず悪事は不問に付され、僕は法的には罰されることがなかった。
しかし、僕は許されたのではなく、何ものかによって「有罪。法的刑罰は無期限の執行猶予。永久に自分で自分を罰すべし」とでもいうべき判決を受けたことに気づくのに、ローティーンの年頃でもそう時間はかからなかった。そのような形で罪の意識が原体験的に初めて、はっきりと発生したのも、この万引き事件においてである。
これでは〝恩寵〟どころか、蛇の生殺しではないか。むしろそれこそ最高の罰、最悪のムラ八分ではないか。もちろん、以後この種の悪事から全く足を洗ったにせよ、また法的に罰されても罪が消えるわけではないにせよ、僕はそれから長い間、あのとき少年鑑別所か少年院にでも入れられていたら、肩の重荷も少しは楽になり、別の人生が開けたかも知れないのに、と内心〝恩寵〟を呪いつづけたものだ。
呪いつづけながら、他方では罰(救い)を求めて罪を繰り返す愚かな人生、それが新たな悪への口実ともなり、生への証しともなったような憐れな僕の人生は、この時から始まった。ただ、罪が町での刑事罰的小悪から人間関係における罪、いわば民事罰的悪事に移っただけのことで、いずれも蛇の生殺し的状況下のそれであることに変わりはなかった。「有罪。永久に自分で自分を罰すべし」なのである。まして刑罰が何やら人間に残された最後のロマンティシズム、つまり、罪に対する一時しのぎの許しの幻想に過ぎないとすれば、なおさらではないか。
3
香港は、いわば全市的な摩天樓の町だ。おそらく、この全市的な摩天樓的景観に匹敵する都市は、少なくともユーラシア大陸には存在しないだろう。空から見れば、なお木造住宅が市街地を隙間なく埋めつくし、大いなる田舎にひとしい東京で、奇妙なまでにアンバランスに屹立する新宿副都心など、ものの数ではない。
そして、九竜側の山の中腹にある展望台で、せまい海峡を挟んだこの摩天樓の町をバックに、中国人女性ガイドが香港の歴史や未来展望をかいつまんで僕らに話した時も、あのジャスミン茶的異和感が僕の胸をよぎったのだった。
話は当然、太平洋戦争中の香港占領ばかりでなく、日中戦争にも及んだが、彼女が日本を非難しなかったのは、職業上の自明の成り行きだとしても、「過去にこだわらず、明日に向かって手をとり合おう」などといったキレイゴトも全く口にせず、ただ淡々と事実だけを言葉少なに語ったのが、僕にはショックでもあり、心の負担にも感じられた。
というのも、金鵄勲章など父のことがすぐ頭に浮かび、その父も僕を含む日本人全体も何やら中国によって、やはり蛇の生殺しのまま放置されているような気がしたからだ。僕はかつて蒋介石が、次いで毛沢東が賠償請求権放棄など、大罪ある日本に示した数々の〝恩寵〟のことを思い出した。そこには当時の国共内戦や東アジア情勢も影響しているとはいえ、その〝恩寵〟の意味するところも、結局はあの「有罪。法的刑罰は無期限の執行猶予。永久に自分で自分を罰すべし」と同じではないか。
彼女は、さらに最近の改革開放政策について少しばかり、かつ自信ありげに語った。彼女が背にした摩天樓群は香港の近代化ばかりでなく、きたるべき中国近代化のデモンストレーション的景観としても、彼女の心で誇らしげに意識されているにちがいなかった。むろん超高層ビルや景観などは二の次で、問題は生活水準の中身だろうが、近年、中国のそれが急速に向上しつつあることは、僕も新聞その他で知っている。
それにしても情報統制の共産主義が、その情報の〝善悪〟は別として、今や近代化の前提ともいうべき情報化社会に転進できるか否かの課題も含め、中国と香港という体制的に異質の両文明は、近代化をめぐってどのように作用し合うのだろうか。もし、互いの弊を矯め合うとすれば、それは一中国の国内問題にとどまらぬ世界史的波紋を生み出すにちがいない。
一党独裁、官僚主義、国営企業の二十世紀的共産主義にも明日はなく、過剰な競争原理、資源の浪費、貧富の大差の資本主義にも未来はないと考える僕は、二十一世紀を新しい共産主義が再認識される世紀と予測するのだが、 鄧小平以降の中国が、その実験台の一つになることは確かだろう。また歴史的にも分裂・分権化しやすく大人口も抱える中国は、これに成功しなければ自滅してカオス(混沌)に戻りかねない。
さて、その夕、新都城酒樓という大きなレストランで、中国古典舞踊を見ながら広東料理の夕食をとるために出かけたノース・ポイント(北角)界隈は、香港島の中心ビクトリア地区の東に連なるのにビル街も古くて低く、何やら恐ろしく庶民的な感じの町だった。そのレストランでは、東京でたまに飲む安い中国酒パイカル(白乾児)を紙に漢字で書いて示したのに、首を横にひと振りしただけで消えてしまったボーイに腹を立て、サービス精神の欠如を言い立てる僕を、同行者は、
「人はさまざま。それより、せっかくのチャンスだから、紹興酒でも飲みましょうよ」とたしなめた。
彼女は、ジャスミン茶にはもちろん、僕が一瞥しただけでもう辟易してしまった、極彩色の樓門や奇怪な石像群のタイガーバーム・ガーデンにも、耳をつんざく鉦やドラや太鼓の古典舞踊にも、さほど抵抗を感じていない様子だった。別れた妻と同様、やはり彼女も戦後生まれの日本人なのである。僕は、ずっと以前、ある外国特派員が「昭和の戦争と敗戦を人生最大の社会的体験として記憶する世代が去れば、日本人ももっと開放的、国際的になるだろう」と書いたことを、回ってくる酔いの中で思い出していた。
「自由と解放を求めてソ連へ逃げたんですって?」
こちらはビールに酔った大きな声で、同行者が反問してきた。夕食後、自由行動ということになり、オプションのビクトリア港ナイト・クルーズをやめにして、同行者とノース・ポイントの薄暗い商店街を歩いていた時のことだ。
「逃げる方向が逆みたい」と同行者は、僕が予想した通りの言葉を、予想した通りの皮肉っぽさで言った。
「どうせ逃げるなら、自由の本場アメリカへ逃げればよかったのに」
僕は酔いの軽口で〝逃れの町〟ソ連へ逃れた経緯の若干を、彼女に話したことを少し後悔しながら、
「あの頃は、まだ若かった左翼の僕にとってソ連は味方、アメリカは敵だったからね。それに仮にアメリカへ逃げたくても、英語は喋れない、何かの特技もない、おまけにカネもツテもないのだから、逃げようがないよ」と弁解した。
「でも、あなたはやがて日本へ追い返されるにしても、とにかくソ連へ、そして、そのあなたを罪の意識でさいなみつづけたとかいう気の毒な奥さんはアメリカへ、つまり、元夫婦が二人とも外国へ逃げ出すなんて、何だか悲しいわね」
「互いにショックが大き過ぎたんだろうな」
「たとえ過去がどうであれ、また相手の国がどうであれ、自由と解放を求めて日本から逃げ出したい気持ちは、私にもわかる気がするけど、どこで暮らそうと、人間である限り苦しみがつきまとうんじゃない?」
彼女に言われるまでもなく、僕も三十過ぎの頃から、いわば自分の罪と文化に対して逃げ場はどこにもなく、どこへ逃げようと漱石の『草枕』の有名な冒頭にあるように、「唯の人が作った人の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい。……越す事のならぬ世が住みにくければ、住みにくい所をどれほどか、寛容て、束の間の命を、束の間でも住みよくせねばならぬ」と一応は人なみに考え始めた時、僕の〝海外逃亡〟の意味がほとんどなかったことにも気づいてはいた。
とはいえ、誰しもまたドストエフスキーの『地下室の手記』のように自分や人間の疑悪醜を、これでもか、これでもかと自虐的に暴き立てたくはないのだから、あの二十代の〝海外逃亡〟も〝海外雄飛〟にすり変え、青春のなつかしいロマンの記憶として神棚に祭り上げ、さわらぬ神に祟りなしで、あれこれほじくり返さないようにしてきたのだった。
しかし、『地下室の手記』ほど気狂いじみてはいないにせよ、なぜか自分の〝海外逃亡〟の真実を見定め、過去の何かにきっぱりとケリをつけたい、との奇妙な情熱が湧き上がってきたのは、おそらく〝逃れの町〟香港の夜の、何やら怪しげな気配にみちた薄暗い下町、という舞台装置によるのかも知れぬ。
僕の〝海外逃亡〟が単なる妻その他への罪の意識、ムラ社会文化の忌避、ロマンや冒険志向のみに起因しないこと、そこにはもっと醜くやりきれない動機がひそんでいることは、当事者の僕自身が一番よく承知していた。ただ、その意識にベールをかけ、中身をはっきり見まいと努めただけなのだ。
一体、僕にとってソ連逃亡とは何だったのか。
ベールを半ば剥いでありていに言えば、失業のないソ連へ行けば食いっぱぐれはないだろう、仕事もクビにならず、また〝アカ〟の前歴も勲章にこそなれ障害にはならないはずで、時に可愛いロシア娘と結婚して、日本での妻との古傷も癒せるだろう、日本語教師としてうまく立ち回ればモスクワ大学教授も夢ではないだろう、などという期待をひそめた逃亡の動機が浮かび上がってくる。
が、それも僕が人にも喋ってきた、おもて向きの動機に過ぎない。そのような世俗の期待の奥にひそむベールをさらに剥ぎ取り、いわば香港という〝逃れの町〟の城壁の縁に手をかけ心の底を覗き込めば、二十代前半の僕、革命運動から追われ、妻とも別れた後の僕が、日本のムラ社会的全体主義という木の檻にうまく適応できず、そこの競争社会すら嫌悪し、かつ恐れて、ソ連という政治的全体主義の鉄の檻に移ろうとしただけのこと。要するにその檻の中の〝社畜〟ならぬ〝政畜〟として、餌と女の安定供給を望んだだけのことではないか。
すなわち、もはや日本では自分自身を律しきれず、自由と解放どころか自分を律してくれる新しい(?)モラルと秩序を求め、比喩的には束縛と禁欲を求めて、さらにはたぶんある種の罰のカタルシスも求めて、〝逃れの町〟ソ連へ逃亡したのではなかったか、という動機の正体が見えてくるのだった。
ノース・ポイントの薄暗い商店街は、商店街というより半露天商街というべきで、歩道脇にはさまざまな商品を並べた露天商が露台をつらね、おそらく夜の時間帯のせいだろう、車道の半ばは臨時の商品置き場になっていた。
どういうつもりか、それがこの場末商店街の流儀なのか、傘を被った電燈たちは両側の商品だけは、まぶしいほど照らし出しているのに、内部は暗く、だから光りは逆光になったり、人間の顔を下から照らしたりして、何やら店員たちはみな無気味なシルエットの印象であった。他の日本人観光客の姿も全く見あたらず、中国人客すらまばらだったから、その無気味さはいっそう際立った。
僕は条件反射の犬のように、〝国際犯罪都市〟香港のイメージを思い浮かべ、昼間カービン銃を肩に九竜の繁華街をパトロールしていた警官たちのことも思い出し、急に不安になった。こういう場合、女性のほうが度胸があるのか、同行者は冷やかし半分で店をゆっくり覗いて回る。
客も少ないのに、なぜかこの半露天商街には奇妙な熱気が感じられた。あえて言えば、何やら人間の心の闇、心の無明をひそめる街の暗がりのあちこちからにじみ出るような熱気、いずれも無言でまとわりつく店員たちの目の光りのような熱気、そう、あのジャスミン茶の匂いにまみれたような熱気だ。ここも 噂に聞いたキャッツ・ストリート、すなわちむかしの泥棒市の同類だろうか。同行者にガードを約束した手前、僕は涌き上がる不安を抑えつつ、この奇妙な熱気はどこからくるのだろう、と考えた。
そして、答えは〝逃れの町〟以外にあり得なかった。例えば客は少なくても彼ら同士、住民同士の連帯と互助で保っているのである。
一般市民も恐れて近寄らず、犯罪者が巣くい迷路も多いというカスバ九竜城も、たぶんこのような熱気にみちているにちがいない、と僕は思った。政庁は香港の近代化と犯罪撲滅のため、九竜城を取り壊すらしいが、たとえ取り壊しても、新たな九竜城がどこかに必ず生まれるだろう。九竜城は〝逃れの町〟の中の〝逃れの町〟、いわば窮極の〝逃れの町〟だからである。
そこが外から見れば不安な恐怖の場所でも、いったん中へ逃げ込めば、被迫害者・被差別者同士の強固な連帯やむき出しの人間性とともに、助け合いや驚くほどこまやかな人情にあふれていることは、僕も学生時代、少し気取ってゴーリキ ー流に〝僕の大学〟と呼んだ日雇い労働者の世界でのアルバイト体験から、多少は知っていた。〝裸〟に近い人間たちの苦楽、哀歓を見せつけられたあの世界も、一種の〝逃れの町〟だった。しかし人間は、まして若者はそこにとどまるわけにはいかず、〝卒業〟しなければならないにしても、その先に何が開けているというのだろう。
4
三日目、三月二十一日、晴天。朝からオプション、日帰りでマカオ見物に出かけた。
水中翼船で約一時間二十分、マカオ外港に着く。香港からついてきたあの中国人女性ガイドは、桟橋前のバス・ターミナルで地元の男性ガイドと交替したが、縄張り主義がよほど徹底しているのか、引き継ぎが終った途端に貝のように沈黙してしまい、僕らが何かを尋ねても、黙ってマカオのガイドを指や目で示すだけだった。
どこか大阪の喧噪と活気を思わせる香港に比べると、いかにも鄙びた、というか風情のあるマカオには、周知の通り聖ポール天主堂跡、孫文記念館、ドッグ・レース場など名所も多く、タイパ島に至る海橋マカオ・タイパ橋のたもとにあるリスボア・ホテルの有名なカジノでは、僕も賭博の真似ごとをしてみた。が、パチンコさえ嫌いな僕には、カジノなど何の関心も湧かぬ。
東京のある友人は「パック・ツアーの海外旅行など絵ハガキよりちょっとましなだけ」と笑ったものだが、当初、なぜかマカオの印象が稀薄だったのは、短い滞在時間のせいばかりでなく、香港でのそれをしのぐ駈け足見物で、僕にはほとんど興味のない、いや小遣いが乏しいので興味の持ちようもない免税店でのショッピングの時間だけが、やたらに長く退屈に感じられたせいかも知れぬ。
マカオのシンボルといわれ、背の高い表壁面だけが奇蹟的に残る聖ポール天主堂の〝残骸〟にしても、映画やテレビで見るよりも実物は意外にちっぽけで、奇蹟の迫力にも欠ける、との感想しか初めは浮かばなかった。
それでも、マカオ南端のバラ岬に近い丘から、狭い海域越しに連なる共産中国大陸のゆるやかな緑のスロープと、五星紅旗らしい赤旗がはるかに望見された時、また、マカオと陸接する中国領との国境関門————僕ら観光客が一定の距離までしか近づけなかった、古い石造アーチの関門を目にした時は、島国に住み〝国境〟感が薄いだけに、ある種の感慨が湧かないでもなかった。
すなわち、これも〝逃れの町〟マカオの入口にふさわしい古びた頑丈そうな、しかし、どこか蠱惑的なアーチ関門を見ていると、僕にはその石門が、悲劇が待ち受けているとも知らずに、テーバイ国へ向かうオイディプスに謎を歌いかけた、あのスフィンクスのようにも思われてきたのだった。〝逃れの町〟をめざす中国人にとって、いずれの側からくぐるにしても、このスフィンクスの門は謎を歌いかけるにちがいない。そして一体、僕にとってのスフィンクスは〝逃れの町〟について、どのような謎を歌いかけてきたのか。
さて、その日の午後、香港に戻った僕らは、今回の小旅行の圧巻となった光景に対面することになる。アバディーンだ。
ビクトリア地区のちょうど裏側の小湾に面するアバディーンは、蛋民と呼ばれる水上生活者が蝟集し、何やら〝竜宮城〟のような水上レストランも海に浮かぶ高名な観光地である。バスに揺られて山を越え、途中、泳ぐにはさすがに季節が早過ぎたが、これも有名な海水浴場レパルス・ベイで少憩した後、アバディーンに入る。
はてしなく再生産される栄養物や排泄物、そして若干の毒物などを黒い波のうねりの上にも下にも浮かべ、というかくわえ込み、いつのまにか溶解し、呑みつくしながら、しぶとく脂っこく生き抜いているといった感じの、汚く猥雑で豊饒な海————その海面を走り回る渡船、漁船、サンパンのエンジンの音にみちた岸壁沿いには、岸からそれぞれの板橋を渡した帆のないジャンクの大群が連なり、甲板に部屋を建て増したそれらのジャンクの多くは、漁業を営む蛋民たちの住居で、船上には犬や鶏の姿も見える。
岸壁では、強引な客引きが何やら叫びながら右往左往し、子供たちは安っぽい土産品を手や肩に、群がる観光客にしつこくつきまとい、時に子猫のように体をすり寄せてくる。
蛋民たちの顔は陽と潮に灼かれて浅黒く、服装も粗末だが、見たところ表情はみな明るくて屈託がなかった。月並な言い方をすれば、それでいて誰もが何やらゴキブリのような生命力をひそめていることが、そういう生命力を失って久しい僕には、直観的にわかったのである。何よりもまず、目の光り方がちがうのだ。
初めは、この猥雑にして貪婪とも見える光景や人間たちに圧倒され、半ば立ちすくんだ僕と同行者も、彼らの生命力に感応したのだろう、やがて自分もその光景の中で生きているような錯覚に捉われ、喧噪の岸壁を同じ一人の人間、いやもしかしたら同じ一匹の動物として、自然にうろつき始めたのだった。そのような旺盛な同化力の雰囲気も、アバディーンにはみちていた。
しかし、その同化力には、開放的な生命力のみにとどまらぬ別のパトスも、明らかに感じ取れた。そう、僕は若い頃に見たアラン・ドロン主演の『太陽がいっぱい』を思い出していた。
あのフランス映画のハイライトは、抑圧的な金持ちの友人の大金と女を奪うため、ヨット上の殺人をなしとげて港町に上陸した主人公が、人間の卑しさ、無気味さ、哀れさを目の隅に(象徴的には、画面の魚市場の露台に並ぶ死んだ魚たちのクローズ・アップでも)現しながら、抑圧者からの自由と解放の喜びを抑えに抑えて、むしろ何ごともなかったかのような顔つきで、露天の市場をさまようシーンだが、港町アバディーンとその住民には、旅行者を比喩的にはドロンの半ば罪障の目が示していると同じ自由感、解放感にひたらせるエトスが歴然と感じられた。これほど露わではなくても、昨夜ノース・ポイントに漂っていた熱気も、おそらく同じ類いのものに相違ない。
聖書によれば、カナンの地やヨルダンの彼方にあるという〝逃れの町〟にいったん逃げ込めば、誤ちの殺人者も(実をいうと狂気による以外、すべての犯罪は、というよりすべての罪は結局のところ〝誤ち〟によるのだが……)罪の追及を免れるという、あのいわば生殺しの自由感、解放感である。演出のルネ・クレールがそこまで意識したかどうかは不明だが、僕にはアバディーンに似た港町でのドロンの目が、まさに〝逃れの町〟をさまよう罪障の目のごとく感じられたのである。
〝逃れの町〟香港の陸上市民からも時に軽蔑され、差別されるというこの蛋民の町は、時に恐れられる九竜城以上に、まさに〝逃れの町〟の中の〝逃れの町〟、生殺しの〝逃れの町〟なのだろう。
人間が内部に神と悪魔を潜在させるからこそ、また(古い言葉を使えば)真善美、疑悪醜を心に同居させ、鋭く矛盾させるからこそ、さらには中国の春秋戦国の古代から文化大革命、その反作用的な改革開放の現代に至る歴史の波乱にも見られるように、政治や文化の行方も一所不在だからこそ、逆に〝逃れの町〟は必需と言えるのかも知れぬ。
そして、今や世界的に政治や文化の行方も一所不在なのである。阿片戦争の因縁以来、長らくイギリスに統治された巨大な自由港香港——中国大陸にとってばかりでなく全世界にとっても、現代最大の〝逃れの町〟の一つであるかのごとき香港を、中国政府が性急に〝解放〟しない理由の若干には、そのような文化的摂理も働いているのではないか。
アバディーンに戻ろう。
「政庁はアパートを建て、陸上生活を奨めていますが、蛋民たちは陸に上がりたがらないようで」と中国人女性ガイドは苦笑しながら説明した。
ガイドによれば、蛋民たちが何世紀も前から水上に住みついた動機には諸説があり、定説はないという。けれども、東南アジアに見られるような陸が湿地のための水上生活でもなく、人口過剰のせいでもない蛋民たちの水上生活の起源が、僕には、当時の漢族の圧迫や漁業の利よりも、自由な密貿易や海賊行為の便に多くあるのではないかと思われた。陸から追われれば海に逃げ、海から追われれば陸に逃げる。
中国名が香港仔、また、阿片戦争以前の香港自身の起源ともいわれるアバディーンは、その意味でも文字通りの〝逃れの町〟なのである。英系最大の企業ジャーデン・マセソンを含む土着香港資本の父祖の大方の出自も、密貿易者や海賊の類いだというが、蛋民に比べたら、彼らは阿片戦争後の新興勢力に過ぎまい。
それにしても、なぜ蛋民たちは陸に上がりたがらないのか。僕のこの疑問は、満艦飾キンキラキンの〝竜宮城〟の水上レストラン海角皇宮に向かう、亀の背ならぬボロ渡船に乗った時、不意に解けた。いや少なくとも僕は、解けたと思った。
それは全くのボロ艀に過ぎなかった。が、艀に揺られているうちに、たぶん〝逃れの町〟のあの生命力やパトスに触発されたのだろう、かつての〝逃れの町〟ソ連をめざした若い日の船旅の記憶が、突然甦ったのである。便乗した船は二千トン足らずの小貨物船ながら、海が一般にないでいたせいか、僕は十余日の航海中、ただの一度も船酔いをしなかった。
船酔いをしなかったどころではない。なぎといっても、外洋は揺れる。士官待遇の乗船通訳で、船中何もすることのない僕には、海はまるで搖籃のように揺れ、充分に夜の睡眠をとりながら、なおベッドで横になり、あるいはソファーに腰を下ろすと、昼間でもたちまち瞼が重くなった。かといって眠ってしまうわけではなく、ただ日常の時間、社会的時間のごときものが消え去り、いわば半覚半睡の無限・夢幻の空間となった僕の脳裡を、それこそ星にまでとどきそうなさまざまな想念が、ゆっくりと流れ動いた。
「いくらすることがないといっても、よくそんなに眠っておれるね」と船酔いに苦しむ同僚が、うらやましそうな顔をしたものだ。
「眠っているわけじゃないけど、船酔いをしないのは、生まれ故郷の家の前にかなり急流の小川が流れていたから、その水の音を子守り歌代わりに聞きながら育ったせいかな」
僕は、たしかそんな返事をしたはずだが、ともかくいわば超時間の無限・夢幻の宙空で、僕の心も体も、かつて経験したことのない心地よい揺曳と安らぎを覚えていた。
しかし、ひとたび起き上がりフロアを歩く時、当然のことながら僕を倒そうとする船の揺れ、波の揺れと絶えず闘わなければならぬ。平地にいるような、比喩的には農民のような安定感は船にはなく、その不断の揺れに無意識に対抗しているうちに、いうなれば揺れに逆らい直立しようとする意思とエネルギーが、そして、やがて始まる外国生活に対する満々たる闘志のようなものが湧き上がってくるのを、僕は感じていた。
艀に揺られながら、その無限・夢幻の揺曳と安らぎ、また、揺れに対する直立志向の闘いの感覚を思い出し、蛋民たちが陸に上がりたがらないはずだ、と僕はうなづいたのだった。岸壁につないだジャンクの家の揺れも、外洋に浮かぶ小貨物船のごときものだろう。そして、考えたら〝逃れの町〟香港の歴史や文化自体が、いや争乱にみちた中国の長大な歴史や文化そのものが、この二つの精神的要素の併立、対立、統合の反復の歴史であり、文化ではなかったのか。
共産主義の現代中国と異なり、自由な香港では、生きるための闘いは熾烈とならざるを得ず、従って、その二つの精神的要素もストレートに現れざるを得まい。ノース・ポイントの半露天商街の暗い熱気もそうだが、アバディーンの目くるめく活気の源泉も、結局のところ、生殺しの〝逃れの町〟を心に抱きつつ自由な人間、解放された人間の内部の、その二つの精神的要素のありようのすさまじさ、すなわち香港人の生の闘いのすさまじさのようなものだろう、と僕は考えた。
時折、潮風に乗って、あのジャスミン茶の匂いが僕の鼻をついた。またか、と僕は笑った。蛋民たちの〝揺れる家〟から流れ出た匂いだろうか。それとも物売りたちの……
「ここでも匂うんだね」と僕は同行者を振り返った。
「何が?」
「ジャスミン茶さ」
「もう慣れたでしょ?」
「どうにかね」と僕は答えた。
ほんとうは、まだそれほど慣れてはいないのだが、仕方なしに朝昼晩と飲みつづけている間に、初めほどの抵抗を感じなくなっていた。三月下旬というのに連日むし暑かったので、喉もむやみに乾いた。汗っかきの体質だから、なおさらである。
香港での耳学問によれば、中国には茶の種類が多く、僕らは半ば偶然ジャスミン茶にぶつかっただけで、町で嗅ぐあの匂いも、実は中国茶の総体的な匂いなのかも知れないが、ジャスミン茶しか飲まされなかった僕にとって、そんなことはもうどうでもよかった。とにかく〝逃れの町〟香港にはジャスミン茶の匂いがよく似合う、と僕は思った。
5
その夜は、最後の自由行動。
ビクトリア・ピークに登る急勾配のケーブル・カーは、山もろとも濃い霧に包まれている。この季節の香港は一般に天候不順で、霧が多いという。僕は同行者と〝百万ドルの夜景〟が眼下に見下ろせるという山頂近くの暗い広場へ出た。
高度のせいか肌寒く、霧が溶けて(それとも小雨が落ちてきたのか)僕らの額や頬をかすかに濡らした。展望台から見下ろす町の灯はぼんやり霧にかすんで、僕らをがっかりさせた。明日の昼過ぎ、帰りの飛行機に乗らなければならない。
「くる時も見えなかった」と同行者がため息をついた。
「今夜が最後だというのに、残念だわ」
「またくるさ」と僕は言った。
何とはなしに、中国人女性ガイドの翳りのある小さな顔を思い浮かべていた。どのような過去から、彼女は逃れてきたのだろう。
別れて二年経った長男に、僕は香港行きが決まってまもなく電話をかけた。先妻、というより子供たちの母親に禁じられているため、母親の不在を確かめての久しぶりの電話だった。
「土産は何が欲しい?」
しかし、長男はそれには答えず、
「お母ちゃんは再婚するかも知れないよ。僕も賛成するよ」と焦ら立った声で言った。
僕は、とっさには返事ができず、子供たちの顔を思い浮かべていた。覆水が盆に返らぬことを、まだ小学生の長男に説明することもできなかった。まして、お前に腹ちがいの妹が生まれたよ、とはとても言い出せない。それにしても僕は、何人の子供を闇から闇へ葬ったことだろう。その長男も、僕との結婚に猛反対する信州の大地主の祖父母に中絶を執拗に迫られながら、母親が必死に守り抜いて生まれたのだった。
獏は悪夢を食べて生きるというが、僕は、象徴的にはあの万引き団事件以来、さまざまな罪を食べて生きてきたことを認めざるを得ない。罪の意識に押しひしがれ、後悔、自責、自罰の念にのたうち回り、年相応に自分の〝顔〟に責任を持つどころか鏡に映さなくても〝鬼相度〟の年ごとの深まりを自覚しながら、罪から罪へと渡り歩き、結果的には心ならずも「子供よりも親が大事」の無間地獄に堕ちる羽目となった悪循環の由来を、いま一度自分に問えば、自明に過ぎるわが身の不徳不実に加えて、これも結果的にはだが、生の悪しきリアリティーとしか言いようがない。
三十代の頃、当時の新聞に連載されたイラン・ルポで、今は日本でもよく知られるようになったアシュラ祭の記事を読んだことがある。イスラム・シーア派のアシュラ祭は、殉教者ホサインの死の無念や苦痛、悲哀を再体験的に分かち合うため、教徒たちが鎖の束で自らの体を叩き、傷つけ、時に血さえ流して殉教者への喪の言葉を歌い叫び、というか歌い泣き、聖廟へ行進する祭りだそうだが、僕はホサインの死が千三百年も昔のことと知って、当初笑い出したものだ。
忘れっぽい日本人————千三百年も前の事件などカスミの彼方で、一宗教、一殉教者の比ではない原爆体験すら半ば忘れかけているかのごとき日本人の一人として、不謹慎にも笑い出してしまったのだが、しかし、この一見自虐の行為が単に殉教者の死を悼むだけでなく、われとわが身の一年の罪障を罰する儀式でもあることを知り、僕には笑いごとではなくなったのだった。ただ鎖の束を使わないだけで、僕もまた罪を犯しては自分を叩き、叩いてはまた犯すという悪循環から逃れ得なかったことを、香港の〝毒気〟にも当てられ、思い出さずにはおれなかったのである。
そういえば、イスラム世界の〝逃れの町〟もアジールというらしいが、日本の宗教では、例えば戦乱の室町期、荘園を持つさまざまな宗派の大寺社が〝逃れの町〟の役割を果たした。教義的には他力本願、ただナムアミダブツと念ずれば悪人でも(いや悪人こそ)救われるとする浄土真宗が、これに当たるのかも知れぬ。僕の家郷の宗旨も浄土真宗だが、僕は宗教に若干の関心は持っても、信仰心のカケラもない。父も、そうだった。
たとえ状況と時代こそちがえ、父もまた戦争という罪を食べて生きる不運を担わされた人間の一人なのだろう。
妻子と引き裂かれ、望まぬ戦場へ駆り出されて、戦うからには鉄砲を撃ち、敵を倒さざるを得ないが、そのことで仮に父が苦しみつづけたとしても、殺さなければ殺されるという戦争は、好むと好まざるとにかかわらず、父の生涯で最大かつ最悪の生のリアリティー、地獄のリアリティーを呼びさましたはずである。そのせいか、父の親友の多くは中国で一緒に戦った戦友たちだった。
この種の生のリアリティーについては、僕にも忘れがたい記憶がある。むろん戦時中のことだが、防空壕で耳をふさいでも聞こえてくる金属音の夕立ちのような爆弾たちの降下音がひびくたび、今度こそ直撃弾だと身をすくめ、胸をふるわせた昭和二十年三月のB29による二度の大空襲に至る約一年間、僕の故郷の町でもほとんど一日おきに敵機の襲来を知らせる役場のサイレンが鳴った。
そのたび小学校の授業は中止されるようになり、生徒たちは校庭で町内会別に集合し、僕ら六年生男子が下級生を引率して、駈け足で避難帰宅した。その中には僕がひそかに想いを寄せる近所の同学年の美少女もいた。
この集団避難帰宅は、僕らにとって異様な陶酔にみちた〝祭り〟のようなものだった。当時は男女別クラスの女生徒にも近づき、気軽に口をきくことができるし、早く家へ帰って遊びに行くこともできる、からだけではない。迫りくるB29の爆音を聞きながら、やはり子供なりに死のイメージをどこかで意識していたし、それがまた美少女への稚いエロスとタナトスのリビドーをかき立てたのである。
だから、それは死のイメージを背に、いうなれば盆と正月が一緒にきたような、いや故郷の祭りに倣えば、水を浴びつつ山車とともに走り回る男性的な〝追い山笠〟と、化粧の匂いや唄、三味線で華やぐ女性的な〝どんたく〟が一緒にきたような感じだった。
敗色の深まりと、運悪く巨大な軍事施設に囲まれた故郷の町への不可避の空襲という予感の高まりから、死を背にした僕らの〝祭り〟は日ごとに興奮と華やぎと陶酔の度を加えて行った。警報のサイレンが鳴らない日は、僕らは教師の目を盗み、おどけて一斉に起立し、 柏手を打ったり〝東方遙拝〟の格好をしたりしてB29の来訪を願ったものである。
やがて、一年近くの高空偵察と威嚇を重ねたB29の、大編隊によるほんものの空襲……。
戦後、僕はさまざまな罪を犯したし、多少の冒険も試みたが、考えたら少年の日々、あのサイレンと空襲への予感にみちた〝祭り〟の日々に感じたほどの生のリアリティーを、単純な比較には無理があるとしても、ただの一度も感じたことがない。
そのような異常な感覚にならなければ、死のイメージや負け戦さに対抗し得なかったのか。それとも、その感覚は僕らがまだ子供に過ぎなかったせいなのか。当時の僕が内心ひそかに期待したのは、いや熱望したのは戦争の勝利や敗北というより、この〝祭り〟の永続であった。
今から思えば、僕の万引き団事件も一面では、敗戦で失われた生の悪しきリアリティーへの、愚かな最初の追跡だったのかも知れぬ。しかし因果応報、僕は故郷を失い、やがて日本も失って、比喩的には、あのマカオ北端に立つ国境関門のごとき〝逃れの町〟の門をくぐり、共産主義国へと逃れたわけだが、それにしてもこの双面神のスフィンクスは、いわば〝さまよえるユダヤ人〟の僕に向かい、ヨルダン川ならぬ日本海を渡って「この地に逃れてくるお前にも、罪障を問わぬ〝逃れの町〟への門は開かれている」と歌いかけたはずである。
しかし、当時の僕は鈍感にもその歌の謎が、僕の〝嫌らしい〟故郷が鼓膜の奥で執念深く歌いつづけるあの歌——すなわち「有罪。法的刑罰は無期限の執行猶予。永久に自分で自分を罰すべし」と嗤い責めるあの歌と、そっくりそのままの判決文であることに気づかなかった。
「風は海から吹いてくる 沖のジャンクの帆を突く風よ 情けあるなら教えておくれ……」
同行者が突然、小声で歌い始めた。その歌なら僕も知っている。戦時中に、たしか日中合作で作られた阿片戦争の映画の時に歌われた曲だ。
「ずいぶん古い歌を知ってるね」
「母が好きだったのよ。母の顔が少し似ているものだから李香蘭の大ファンでね」
僕も見た憶えがあるのだが、そうだった、李香蘭はあの映画に出ていた。広州と香港が舞台で、清末の英雄林則徐らの反英闘争と中国人難民姉妹の苦難の物語といった映画だったと思う。エキゾチックな美貌と才気で満映のナンバーワン女優と謳われた李香蘭、後 の山口淑子自身、日中間の激動の嵐に翻弄された、文字通りの政治難民だったのだろう。
「風が吹いて、この霧を吹きとばしてくれないかしら」と同行者は言った。
風はほとんどなく、視界を覆う霧は薄れるどころか、むしろ少しずつ濃くなって行くように見える。
「今まで歩いて、どこが一番面白かった?」
同行者が質問してきた。
「もちろん、アバディーン。きみは?」
「アバディーンも面白かったけど、私はマカオの、あの高い壁だけで立っている天主堂が一番印象に残ったわ」
「ああ、あの原爆でやられたみたいな……」
僕は、戦後の長崎で見た浦上天主堂の残骸を一瞬思い浮かべて、そう言った。
「昔の日本のキリシタンも、あれを建てるのを手伝ったそうだけど、その人たちが一生日本に帰れなかったことを思うと、何だか可哀そうで、余計に印象に残ったのよ」
同行者の表情は、意外に生真面目な感じである。僕は、聖ポール天主堂の〝残骸〟を頭に描いた。秀吉、家康の禁教令から逃れた長崎のキリシタンたちが、この天主堂建設に参加したことや、百数十年前の台風で崩壊し、表壁面だけが残ったことは、マカオの中国人ガイドも説明していた。
「ピサの斜塔じゃないけれど、よくまあ、あんな格好で倒れずに立っているわね。きっと、日本のことを思いながら異郷で死んだキリシタンの心が、天に通じたのよ」
「天に通じた、か」
僕の心が少し動いた。そういえば、あの天主堂はおかしな建物というほかはなかった。背が高く、薄く、また尖塔なども持つ不安定な表壁面より、はるかに丈夫なはずの天主堂本体のほうが台風で崩れ、表壁面だけが立ち枯れのように、何かの思い出のようにやっと残っている、いやたとえやっとでも、本体〝没後〟の百数十年間の台風その他をしのいで、丘の上にぽつんと立ちつづけているというのも、やはり一種の奇蹟のようなものかも知れぬ。
僕がそう思ったのも、自分も人間の本体、実体のごときものをとうに失い、あの表壁面のような〝残骸〟として生きているのではないかという不安、戦後ずっと意識の底に見え隠れしながらつきまとってきた不安が、反射的に甦ったばかりでなく、とにかく表壁面だけでも倒れずに立っている何やらわびしげな実在感が、わが身に合わせて連想されたからである。
「昔の人は偉いと思うわ」と同行者はつづけた。
「信仰のためとは言っても、あなたのいう逃れの町のポルトガル領マカオにまで命がけで逃れてきて、あんな立派な天主堂を作ったんですもの」
僕が彼女の言葉にほんの少し感動さえ覚えたのは、あの天主堂の奇蹟的な、というよりどこか近現代人的な、いわば本体なき不倒壁のイメージや、見下ろす下界は白い夜霧の海という、神秘めいた雰囲気のせいもあるだろう。が、四百年近くも昔、文字通り正真正銘の〝逃れの町〃をめざした日本人の真摯、必死の生き方が胸に伝わってきたのも確かだった。まして彼らはポルトガル語も広東語もほとんどわからないのである。
僕は最近急に興味を持ち始めた、乱世といわれる中世後期の日本人のことを考えた。一向宗(浄土真宗)やキリシタンも含め、当時の日本人は信仰心にも厚かったが、今の日本人からは想像もつかないほどの、強靭な文化的生命力も持っていたのである。現代へとつづく偉大な室町文化も、その生命力の表出にほかならぬ。
江戸中期の儒者にして政治家の新井白石は、中国人と日本人の相違を「中国は方にして渋れる。日本は円、温にして和」と評したが、そしてこの評は半面の真実を伝えているが、少なくとも日本人に関する限り、それは江戸期や明治以降の日本人評というべきで、中世後期の日本人は「方にして渋れる」——つまり原則を守り自己主張も多い個人主義者、という側面も兼備していたはずだ。そうでなければ、あの長い乱世は生きられないし、あれほどの信仰も生まれまい。
マカオに逃れてきたキリシタンも、信仰に厚かったばかりではなく、「方にして渋れる。円、温にして和」という二つの特性を兼備融和するほどの文化的生命力にみちた日本人たちであったろう。当時の宣教師たちが他のどのアジア人にもまして日本人を高く評価した、いや時にヨーロッパ人以上とも評価したゆえんは、まさにそこにある。「方にして渋れる」だけではヨーロッパ人、中国人の亜流に過ぎず、「円、温にして和」もその半面が閉鎖的・排他的・独善的で文化的生命力も脆弱なムラ社会文化だけというのでは、これまた高く評価しがたいのである。
そう考えると、これも昔から器用だったにちがいない日本人が、あの丘でこつこつと天主堂の石を削り、像や紋様を刻む姿も目に浮かんだ。そして僕は、暴政に抗するキリシタンなど一揆勢三万七千余が、女子供まで含め皆殺しにされたという島原の乱に、黒田秋月藩の士族だった父方の先祖が、幕府軍の一翼として出陣したことも思い出していた。まさに象徴的には、このジェノサイド(大虐殺) こそ中世後期の文化的生命力にトドメを刺したのだ。同行者のことも忘れ、僕はその悲劇的なダブル・イメージのキリシタンの姿に向かって、心中思わず合掌していた。
それに引きかえ、自分という人間は一体何をしてきたというのだろう。同じ〝逃れの町〟をめざした逃亡者でも、月とスッポンではないか。
たとえ一事でも、人の役に立つことをなしとげたか。たとえ小事でも、果たすべき義務を貫いたか。まるで小悪、小害をばらまくために生まれてきたようなものではないか。〝カネがすべて〟のからっぽ人間よりも、もっと悪い。僕は、柄にもなく頬を赤らめた。今度の小旅行も、実は観光旅行などというものではなく、心貧しく見すぼらしい自分の正体を、〝逃れの町〟香港・マカオという鏡に映しにきただけではないか、というほろ苦い、しかし、ちょっぴり心が洗われるような想念が、僕の胸をひたした。見方によれば、わずか三泊四日ながら、それもある種の〝観光〟旅行にはちがいない。
「日本に帰ったら、まずサングラスを外すぞ」
僕は、唐突にそう叫んだ。鬼であろうと蛇であろうと、まず自分の素顔をさらけ出そう。
「そんな度の強いメガネを外して大丈夫?」
同行者は、僕の顔を見上げた。同じ度数の普通のメガネも、家に置いてはいるのだ。ただこの十年来、普通のメガネを外でかけたことはなかった。
「せっかく似合うサングラスなのに」と同行者がからかうように笑った。僕は黙って苦笑を返す。
その時、不意に強いジャスミン茶の匂いが、どこからか漂ってきた。それはジャスミン茶の匂いというより、何やらもう動物の体臭に近いほど強烈な匂いで、僕は一瞬、軽い眩暈を感じたくらいだ。
「ジャスミン茶の匂いがしない?」
僕はアバディーンの、あのいわば動物的な光景を思い出し、なぜか少しどぎまぎしながら同行者に尋ねた。
「しないわ。……ここは五百何十メートルという山の上よ」
おそらく彼女の鼻は、化粧でバカになっているのだろう。僕は、奇怪な生きものを見る思いで、霧の彼方の香港の町をすかし見た。この巨大な〝逃れの町〟、化けもののような町に漂うジャスミン茶の匂いという匂いが、じっとりと夜気の淀んだ海峡の上、港の上を白い霧と化し、一団となって立ち昇ってくる幻覚に、僕は捉われた。これが僕のスフィンクスが歌いかけてきた最後の謎なのか。風がなく、湿気も多いせいではないかと思いながらも、僕はその無気味さにたじろぎ、「香港の匂い、逃れの町の匂い……」と胸の奥で半ば邪気払い、鎭撫の呪文のつもりでつぶやいた。
それにしても、こんな山の上にまでジャスミン茶の匂いが流れてくるなんて……。僕は訝り、その強烈な匂いに息をつめながら、次の瞬間、はっとした。あわてて指でサマージャンパーの襟を持ち上げ、自分の胸元に鼻を近づけると、もうもうたるジャスミン茶の匂いは、僕の体から立ち昇っているのだった。(昭和58年6月)
この作品は「流星群9号」に掲載したものを加筆して転載。
一輪の椿の花を秋月に
〒340-0154埼玉県幸手市栄4-3-504
TEL0480-43-5599
新納三郎宛
――三人の息子へ――
秋月といっても、その名を知る人はほとんどいないにちがいない。私の生まれ故郷――福岡県朝倉郡秋月町は、九州最大の筑後川の支流小石原川の、そのまた支流野鳥川(別稱秋月川)が削った小盆地に抱かれる山深い廃邑で、明治維新までは黒田支藩五万石の城下町だった。
秋月の名が、まさに消えなんとする近世史に最後に登場したのは、明治九年十月に起こった秋月の乱によってである。旧藩士の半分に近い二百五十余人が総大将今村百八郎らに率いられて、東京の新政府に反旗をひるがえした。私の父方の曾祖父武田勝右衛門も、この反乱軍に加わっている。が、乱は数日にして鎮圧され、今村らは斬られ、私の曾祖父は自殺した。ほとんど同じ頃、互いに呼応して熊本では神風連が、萩では前原党が決起したが、これも一両日のうちに鎮圧された。西郷の鹿児島挙兵は、その三カ月後のことである。
昭和の高度成長は、いわゆる過疎地の問題を全国的に生み出したが、秋月は、維新以来現在に至るまで、一貫して過疎の道をたどりつづけた町である。ツゲの原生林で知られる古処山を背に、三方を山に囲まれた孤絶的な要害という地勢のため、高度成長どころか明治の〝文明開化〟からさえとり残された。
維新までは、南一里半の福岡藩領の商人町甘木と比肩されつつ「甘木千軒、秋月千軒」といわれたらしいが、維新このかた人は四散し、武家屋敷の大半も石垣囲いの田畑となり、十文字にのびた坂の往還沿いとそのわずかな裏側に、わびしげな町並がただひっそり連なるのみである。人口、二千足らず……。むろん汽車もなければ電車もなく、甘木から上ってくるバス便があるだけで、財政不如意のせいか、今では町そのものが甘木市に併合されてしまった。
いくら財政不如意とはいえプライドを捨て、なぜ甘木との併合の道を選んだのだろう。秋月周辺の同じ郡下の村々――上秋月、安川、小石原(北部)と統合して、なぜ観光立町その他による独立自尊の道を考えなかったのだろう。〝時間〟との近代化流の闘いに敗れただけで、秋月は、それほど足早に消え急ぎたいのか。かくいう私の生家も跡を継ぐ者がなく、母屋は とうに消え果て、残った離れも朽ちかけている。
全国に旧城下町は数多いが、秋月ほどみごとなまでに〝時間〟が停止した町、というか死者と生者の境界が分かちがたく入り混っているような雰囲気を漂わせる町も、そう多くはないだろう。崩れかけた土塀の蔭から、島田髷の娘がひょっこりあらわれても、すこしも不自然ではない町のたたずまいは、萩や津和野と変わらない。
けれども、新政府に半ば強いられた秋月の乱の血の犠牲は報われることがなく、鎮撫されることすらなくて、一世紀余を深まる過疎の中に打ち捨てられてきた運命への怨念の気配が、風化につぐ風化で自然に還りつつあるかにみえる廃邑のそこかしこに、また、文明の穢れを知らぬ山の緑や川の瀬音にも、かえってくっきりと浮かび上がっているような、そういう雰囲気なのである。
町の東側に位置する秋月城跡、というよりは舘跡には黒門や長屋門、カズラの這う石垣、苔むした石段、濠などが残っている。濠端に沿う通りは今は桜の名所だが、昔は杉並木で馬術の稽古も行われ、杉の馬場と呼ばれていた。町の裏手を縫う鄙びた小路は、いずれも水気を含んだ白い砂道で、踏んだ感触がとても柔らかい。大路小路の両側には、そのまま掌ですくって飲めそうなせせらぎが、かすかな音を立てて流れている。
戦後だいぶ経ってからも、私の今は亡い祖母や伯母、叔父たちは、波のきらめきに小貝が揺れ、さわ蟹が砂地を這う家の前の渓流で歯を磨き、顔を洗い、食器をゆすいでいた。裏の井戸がやや不便だったせいもあるが、それほど水は清らかだったし、いまも清らかである。川を汚さないというモラルも、ごく自然にだれもが身につけていた。食器洗いや洗濯も含めて、それぞれの時間帯が不文律として定まっていた。
秋月には、どこの旧城下町もそうであるように、寺が多い。私の生家のある石原、鳴渡界隈は〝寺町〟のごとくだ。その一つ――曹洞宗長生寺の納骨堂で、私の曾祖父は同胞たちとともに眠っている。戦い敗れて政府軍に投降した曾祖父は、福岡への押送の途上、博多に近い板付で自殺したのだが、遺骸は何日も野ざらしになっていたという。見せしめのため、そうされたのかも知れない。大黒柱に死なれた家族は、一家離散の羽目となった。孫や曾孫の代まで貧苦はつづき、末の叔母を除き孫の代でも中等教育さえだれも受けられなかった。
秋月にはまた、椿が多い。山の緑、道の白砂、せせらぎの音と光りに縁どられたこの廃邑に、椿の花はよく映える。それにしても散るというよりは、首がもげるようにして落ちる椿の花を不吉とした士族の町に、どうしてこんなに椿が多いのだろう。
秋月の東一里半、小石原川が刻む上秋月の江川渓谷にある栗河内の陋屋で、故郷をめざして敗走してきた秋月党のうち、リーダー格の宮崎車之助、哲之助兄弟ら七人は切腹して果てた。一番若い哲之助は六人を介錯したあと、ただ一人腹を切り、さらに 自らの首を刃に打ちつけ、喉の皮一枚を残して自刎したという。時に、数えで二十五歳。
郷土史家の採取に成る当時の農民の証言によれば、七人は近くの農家からよせ集めた濁酒を酌みかわし、今生の別れのささやかな宴を張っている。やがて数番の謡曲が聞こえ、その声がやむと、ゴトン、ゴトンと何かが床に落ちる重たい音がひびいたあと、それきり物音も絶えて秋の夜の静寂が戻ってきたという。哲之助の兄、そして車之助の弟にあたる今村百八郎は、手勢を率いてなおも戦いつづけたが、結局捕えられ、こちらは福岡の桝木屋の浜で、参謀格の益田静方とともに刑吏に首を刎ねられた。
乱後、彼らの遺骸は遺族の手で仮埋葬地から掘り起こされ、あるいは福岡その他から荷馬車で故郷に運ばれた。遺族は、彼らを秋月の清らかな水で洗い浄め、線香をもうもうと焚いて死臭を防ぎつつ、柄杓の柄を差して首と胴をつなぎ、その上を包帯でぐるぐる巻きにして生前の姿に戻し、埋葬した。宮崎、今村三兄弟の墓は、現在も長生寺の墓所に並んでいる。
下級士族である武田家の墓地は、町の西側の白石の山腹(古賀ん谷)にあったが、昭和四十年前後の高度成長期に長生寺に新設の納骨堂へ改葬された。秋月の乱では、秋月党だけで三十六人の死者が出た。これは島原の乱に出陣した折の死者三十五人とほぼ同数だが、小藩にとってはかなりの犠牲者なのだろう。
それから、百年余の歳月がたつ。栗河内のすぐ下流から、いまでは江川ダムが湖水に緑蔭を映しながら広がっている。秋月の乱は、戦前は反政府という理由から、戦後は不平士族の反動という評価から、深い忘却の湖底に沈められたままである。そして、士族の大半がその妻女ばかりでなく、自らも手内職や畑仕事に励まなければ生活できないほど貧しかったという事実には、だれも目を向けようとしない。たしかに軽挙妄動、短慮暴発の謗りは免れないにせよ、その貧しい生活すら満足な補償もなしに奪われようとした時、彼らは起ち上がったのだった。
軍法会議ともいうべき福岡臨時裁判所で、「除族の上斬罪」を申し渡された今村は、数えの三十五歳という若さで世を去ったが、この今村の墓に、お高祖頭巾姿の若い女性がしばしば詣でていたという。彼女は今村の愛人幾知で、甘木の三味線屋の娘である。甘木の花とうたわれた美女だったらしく、刑死した秋月党の御大将とのロマンスは、わらべ里唄となって、いつまでも歌いつがれた。
甘木四日町 三味線屋
お幾知ちゃんは 思案顔
士族今村 首があったら
よござんしょ
お幾知 可愛いや
花桶さげて 墓参り
士族今村 さぞやあの世で
うれしかろ
今村は出陣の折、幾知を呼んで形見に無銘の業物を与えた。やがて幾知の生家が傾き、形見の短刀は近所の質屋の手に渡った。幾知は法務官石田某と結婚して故郷を去ったが、愛人の形見さえ手離さなければならないほど落ちぶれたのか、それとも新しい愛人の法務官に義理立てしたのか、いまはいずれとも判じがたい。
さらにそもそも、今村を殺した官憲側と同類のごとき法務官と、なぜ結婚する気になったのかも、不明である。しかし、わらべ里唄の「思案顔」という言葉に、女心の機微も多少は推量されていよう。形見の短刀は、時代の流れとともに人から人の手に移って、最後は太平洋戦争に出征する軍人の守護刀、つまり今村の霊魂がこもった破邪の剣として戦地へ持ち出されたというが、その後の消息は知れずじまいである。
わが国には〝小京都〟を自任する町が少なくない。秋月はその中でも、もっとも小さな、かつもっともさびれたモデルだろう。が、秋月美人の伝統だけは、他のいかなる 〝小京都〟にもひけをとらない。因みに秋月という地名は、鎌倉時代から戦国時代までこの地で活躍した大守秋月氏に由来する。戦乱にも明け暮れた秋月氏の最盛期は公稱三十六万石に及び、秋月文化が栄えたというが、秋月美人は、じつはこの秋月氏以来の伝統なのである。
しかし、薩摩島津氏に味方した秋月氏は秀吉に追われて、わずか三万石の日向高鍋に去り、代わって黒田氏が入国してくるわけだが、 秋月に最初に入った黒田惣右衛門は、福岡藩祖黒田長政の叔父でクリスチャンだったせいもあり、秋月氏末期から慶長期にかけての秋月文化には、私の生家に近い鳴渡の切支丹橋、教会堂跡、また切支丹灯籠などの遺物にも見られるように、南蛮文化の光りも当たっていた。江戸初期の禁教直前の秋月領だけで、二千人ものキリスト教信者がいたといわれる。
鎖国後も秋月黒田藩がしばしば長崎警固の任につき、また文化七年(一八一〇年)に長崎から石工を呼んで、長崎のそれと同じ名と構造を持つ石材アーチ式の眼鏡橋を野鳥川に架けたのも、秋月の文化伝統と無縁ではあるまい。その時以来、眼鏡橋は古処山とともに秋月のシンボルとなっている。
先の秋月氏が生んだ第一の傑物といえば、だれしも上杉鷹山を挙げるだろう。高鍋藩の六代目秋月種美の次男治憲、すなわち後の鷹山は九歳にして上杉家の養子となり、明和四年(一七六七年)十七歳で米沢藩主となるや、終生の師である儒者細井平洲らにも援けられて、十余年に及ぶあの「なせば成る なさねば成らぬ何事も 成らぬは人の なさぬなりけり」の大改革を成就した。その母は秋月黒田家の娘春姫だから、鷹山にとって秋月は父祖の地であるばかりでなく、母の実家でもあったことになる。 なお、鷹山の甥の秋月幸三郎は高鍋藩から秋月黒田家へ養子に入り、第八代黒田長舒となった。
秋月氏が古処山に山城を築いた時代から数えても、八百年近い歴史を持つ秋月にとって、明治維新は文字通りの晩鐘であり、秋月の乱は文字通りの挽歌であった。町の西北郊石原にある私の生家の前を通って秋月街道を西へ進むと、道はすぐ山に入り、谷間をつずら折りに蛇行しながら高みへと登って行く。道端には苔むした小さな墓地や棚田、棚畑が点々とつらなり、木洩れ陽を受けた急流が時折キラリと刃のように輝くのである。
振り返るたび、秋月の町は山蔭に見えなくなったり、不意にあらわれたりしながら、下方へ下方へと沈んで遠ざかる。そして、町の姿を最後に見下ろせる坂を、涙坂という。参勤交替などで江戸へ行く者は、ここで涙を流し、江戸から帰る者も、ここで涙を流した。
秋月党はなぜかこの涙坂を避け、南の急峻な間道である甘水谷を登って進軍した。裏切られるとも知らずに豊津党(旧小笠原藩)と合力すべく豊前をめざし、さらには同時に敗北するとも知らずに長州の前原党と海路合流して、西郷の決起を促しつつ東京への先陣を駈けるため……。しかし結局、秋月党は豊津近郊の錦原で、若き日の少佐乃木希典もいたという新式装備の政府軍に完敗し、故郷への敗走をつづける羽目となる。
故郷秋月はすでに官憲に占領され、住民たちは郊外へ避難するなど動乱の中にあった。かくして今村百八郎は、ついにその妻子にも愛人幾知にも、生きて再びまみえることがなく、私の曾祖父も数えの四十七という分別盛りでありながら、若い妻と三人のおさな子を再び見ることがなかった。
同じ時代、同じ理由で乱を起こしながら、佐賀や萩や鹿児島には、むしろ維新の勝者の匂いのほうが色濃く漂い、熊本でも五十四万石の旧大藩の繁栄が現在までつづいているが、ひとり秋月のみ時代の手によって完膚なきまでに滅ぼされた。
「お前んひいじい様はな、サムライらしゅう立派に腹ば切って死んなさった」
祖母は子どもの頃の私に、彼女が幼時見聞したという秋月の乱の話を、そういう切り出し文句で始めたものである。高手小手に縛られて、いや少なくとも両手首を厳重に縛られて押送される曾祖父に、切腹の機会などあるはずがないことは自明だが、おそらくは何か突発的な原因から舌を噛み切っての憐れな自殺か、あるいは押送途上での官憲による密殺が、子や孫の間で語りつがれているうちに、武士らしい「切腹」に美化されたのだろう。
覚悟の自殺ならば投降前にいさぎよく実行したはずだし、そうではなくて、他の多くの秋月党士と同様、妻子など家族と生きのびる道を選んだからこそ、投降して福岡の裁判所へ押送されていたはずではないか。だから押送途上での、下っ端党士の曾祖父の自殺が何とも解せないし、納得しがたいのである。それに遺骸は、なぜ何日も野ざらしにされたのだろう。密殺され野ざらしにされるほど、曾祖父は何らかの言動で官憲の怒りを買ったのか。
しかし、他方投降したという確かな記録も残っていないのである。だから実は何かの目算があってか、曾祖父はただひたすら西へ(たぶん博多に向かって)逃れ、板付までたどり着いたところで、もはや逃げきれぬと観念して首をくくったのかも知れぬ。記録によれば、曾祖父の死に方のみ戦死や敗走途上の自害、斬殺、切腹、自刃ではなく「自殺」とある。つまり、いずれにせよ刀による武士らしい死に方をしなかったのだ。
私は、曾祖父の死の真相について刊行物でいろいろ調べたし、福岡や甘木の裁判所、警察などに何度も文書で問い合わせたが、あまり古いことなので資料が残っていない、という返事であった。歴史を長いスパンで見る癖のついた私には、明治の初期などさして古いことにも思えないが、頭の片隅から私を押しとどめる声――「死者を暴くな。ただ静かに眠らせよ」との声が聞こえてくるのも、また事実である。
そう、じつは切腹であろうと自殺であろうと密殺であろうと、まさに秋月はだれもかれもが、ある意味で「腹ば切って」死に絶えることによって、逆に不動の生を生きつづけているような、いわば鷹山とは正反対の無明のなつかしさをたたえた町なのである。
参考資料 田尻八郎『秋月党遺聞』郷土文学社
三浦末雄『物語秋月史』秋月郷土舘
筆者注――本篇は「経済と文化」昭和55年1月号掲載の同題のエッセイを、史実誤認その他の不備不足を改めて文芸誌「流星群13号」に再掲したものです。
大沢久美子の本
ここに六冊の本がある。一九八九年発行の『絆』から始まって、『二枚の画布』『黒い花』『イブを見た女』『父の乳房』『詩集 小さな溶鉱炉』と毎年一冊のペースで発行してきた手作りの本である。
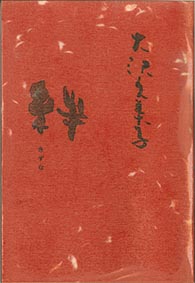 |
 |
 |
 |
 |
 |
私は勤めを持ちながら小説を書き続けていた。最初の頃は漠然とした作家志望という夢を抱いていた。それがやがて生きることがすべて書くことにつながってしまうようになった。書くことによって自分の生きざまを見つめ、人間社会のあり方を考え、辛いことや苦しいことに立ち向かうことが出来た。
「日本随筆家協会」「立像」「現代文藝」と書く人たちのグループに所属して、同人雑誌に作品を発表し続けた。それらの作品は「文学界」の同人雑誌評に何度か取り上げられ、今月のベスト5に選ばれたりもしたが、それだけのことでこれといって話題になるようなこともなく、作品は溜まっていく分、作家志望の夢は色あせていった。
食うために働くといった漠然とした生活に疲れれていた。何か自分の生涯をかけて出きることはないかと思うようになり、とりあえず一年に一冊自分の作品を本にするために働くのだという目標を立て生きてみようと考えた。
 |
 |
 |
「風の宿」「他人の城」「風の女」と日本随筆家協会から立て続けに出版した。それらはすべて私の父に表紙絵を描いてもらい、原稿を渡したら何ヵ月か経って本が出来上がってくるという他人任せのものだった。初めの一冊には感動があったが二冊三冊となると感動は薄れていった。二冊目の「他人の城」は、表題作が第十三回埼玉文学賞を受賞しており、出版記念会も経験した。テレビドラマ化の話があったと発行所から連絡を受けたがその後の経過は音沙汰無しだった。本は全国図書館選定図書にもなった。
その後、ワープロを使用するようになり、所属していた現代文藝研究所で発行していた文藝ジャーナルや同人誌、作品集などの印刷物を印刷所に出さずに研究所で作ることになり、出版部門を「現代文藝社」として、私はワープロで版下を作ることを手伝うようになった。
製版、印刷、製本の試行錯誤を繰り返す中で主宰者が、毎年発表した作品を一冊の本にしたいという私の意向を汲んで、研究所で出版したら自分の思い通りの本作りができると助言してくれた。
現代文藝研究所の事務所は、九畳ほどの狭い空間にコピー機や印刷機、帳合機、応接セット、冷蔵庫、本箱、ワープロ、主宰者の机や椅子など雑然と置かれて、より良い本作りのために何かしらの機器が毎年のように取り替えられ増えていき、その返済に主催者は四苦八苦していた。
事務所のベランダに向いた窓はいつも半分開けて、下の方に二〇センチ四方の穴があいた木の雨戸で塞いであった。その穴から主催者の飼い犬や近所の野良猫が出入り出来るようにしてあるのだ。犬や猫たちは好き勝手に出入して、印刷中のインクの中に足を突っ込んだり、帳合している印刷物の山を崩したり、とにかく本を作る環境には程遠いものだった。それでも主宰者は平然として、その邪魔者たちを追い出そうとはしなかった。
仕事が終ると酒盛りが始まる。電気コンロに鍋をのせ、仕事が始まる前から煮込んでいた煮物ができあがっている。缶ビールと焼酎を飲みながら鍋をつついて本作りの話に興じる。匂いを嗅ぎつけて、雨戸の穴からあるじの飼い犬や近所の野良猫たちが入って来て、スキあらばと酒のつまみを狙っていて、油断ならない事態になる。しかし、仕事を終えた充実感はほろ酔い気分の心も体も満たしてくれた。
できあがった本は、版面が不揃いで、ペラペラと捲るとページが踊っていたり、インクの濃さがページによってばらついていたり、同じページ内での印刷むらがあったりとなかなか思うようにはならなかった。表紙についてもハードカバーをどのようにするか、紙質をどうするか、製本の綴じ方など、難問が次から次と立ち塞がった。
二百頁を百部ほど手作業でやる帳合は、辛抱のいる作業で、いくら自分の本と思っても苦痛であった。なぜかといえば、ページの組み違いが不安なのである。何回も見直しを繰り返すことになるのだけれど不安が解消されるどころか、見直せば見直すほど新たな不安がつのってくる。できあがった本までもページの点検をすることになってしまうのだった。これに懲りて帳合機を購入したが、この不安は解消されなかった。
これでは他人の本を手作りして、渡してしまったあとまでも不安をひきずることになってしまうのではないか。そう考えると代金の請求などとてもできないことだった。これが六冊の手作りの本作りを体験しての実感だった。
それでも自分を含めて物を書く人の立場に立って考えて見ると、どうにかして作品を本にしたいという思いは切実で、その思いに何とか応えたいと願う主宰者の気持ちが、自費出版の仕事を手がけることに踏み切らせた。
出版がなぜ高いのか、手の届く価格はどれぐらいなのか、どうしたら安くて良い本が出きるかなど、私は主宰者とともに自費出版を手がけるにあたって、書き手の思いが反映される自費出版とはどういうことなのかいろいろ考えさせられた。
人は雇わない。印刷、製本は外注に出すが、できるだけ良い本作りを理解してくれる安い所を探す。表紙を一色刷りで見栄えの良いものはできないか。宣伝は公募ガイド一本にする。販売のルートは持たないことをはじめから明確にして、著者の必要部数のみつくる。料金表を提示する。
筆者の立場に立てば、自分の作品がより多くの人に読んでもらえることが出版の目的でもある。しかし、この要望に応えることは、今日の出版事情から考えても難しい。売れない本を承知で何千部もこしらえて、結局処分せざるを得ないのだったら、無駄な経費は省く方法を取る。
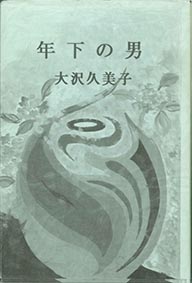 前記したようにはじめから販売はしない、売るための宣伝もしない、ということを明記して経費をかけない分、出版費用の軽減をする結論を出した。そのかわり、研究所で発行している文藝ジャーナルや研究生募集広告を活用して、本の発行をささやかではあるが世に知らせることにした。
前記したようにはじめから販売はしない、売るための宣伝もしない、ということを明記して経費をかけない分、出版費用の軽減をする結論を出した。そのかわり、研究所で発行している文藝ジャーナルや研究生募集広告を活用して、本の発行をささやかではあるが世に知らせることにした。
ようやく先の見通しが立ち、計画が少しずつ具体的になって、何冊かの本を作り軌道に乗り始め、現代文藝研究所の出版部門だった「現代文藝社」は、私に任されることになり独立した。
それから一年が経過して、 現代文藝研究所の所長であり、同人誌「現代文藝」の主宰者でもあり、一九八〇年から文学の指導を受けていた恩師田端  信先生は、癌で亡くなった。 その間に私は自分の祖父をモデルにした四百字詰め原稿用紙三百枚の小説「葦の原の夢」を出版に向けて推敲している段階だった。
信先生は、癌で亡くなった。 その間に私は自分の祖父をモデルにした四百字詰め原稿用紙三百枚の小説「葦の原の夢」を出版に向けて推敲している段階だった。
田畑先生は病院のベッドで死の病と戦いながら、最後までこの小説のことを気にかけてくれていた。
「これを書き上げたら次のステップだ」
師はまるで、じきに退院して次の作品の指導を楽しみにしているような口振りなのであった。 あれから四年の歳月が経とうとしている。手作りの六冊の本が生まれた部屋は今はない。しかし、あの狭い事務所で師と暴れ回る犬や猫たちと共に本作りをしたその志は、「現代文藝社」として今も私の中に受け継がれている。(自費出版ジャーナルに掲載)
