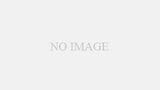12月24日(火曜日)。強い寒気が起き立てのわが身に沁みている。私は寒気に音を上げそうである。バカなことを言っちゃいけないよ。このところのテレビニュースは、日本海側の降雪量の多さや雪の嵩(かさ)の高さを報じている。きのうのニュースには、屋根の上の雪下ろしで、亡くなられた人のことがあった。きわめてつらいニュースだった。それでも人は生まれた所に住み、職業や仕事の都合で離れても、だれにもそこは愛(いと)しい生誕地であり、ふるさとである。だから、他人行儀に今はやりの移住の進めや、見せかけの同情は禁物である。
これに加えて私は、こんなことを浮かべて起き出している。遠いわが子どもの頃、すなわち児童(小学生)や生徒(中学生)時代の教育現場にあっては、盛んに情操教育という言葉が囃し立てられていた。しかしながら私は、その真意を知らないままに、とうとう人生は終末にある。情操教育を見出し語にして、電子辞書を開いた。
【情操教育】:「創造的・批判的な心情、積極的・自主的な態度、豊な感受性と自己表現の能力を育てることを目的とする教育。知性・道徳性・美的感覚・共感性などの調和的な発展を狙いとする」
書くだけで骨が折れて、説明文もまた珍紛漢紛(ちんぷんかんぷん)であり、もとよりわが身には無縁である。現下の学校教育の目標(スローガン)は知る由(よし)ないけれど、老若男女(ろうらくなんにょ)並べて、デジタル社会だということは知ることができる。
きのうの私は、いつもの大船(鎌倉市)の街へ、買い物に出かけた。わが買い物は往復共に、20分ほどバスへの乗車が強いられる。私は、二人座席の空いている奥の所に腰を下ろしていた。そして、スマホを片手にして、この日書いた「ひぐらしの記」を読んでいた。文章の校閲を主眼とする、半ば楽しいひとときである。途中から親子連れが乗り込んで来られて、娘はわが隣に座り、両親は娘を囲むようにして立たれた。両親は立ったまますぐに、それぞれがスマホを手にされて、何かを見始められた。座席の多くの人たちもスマホを見ている。立っている人たちもチラホラ、スマホ見ている。もはや、異常な光景ではなく、普段、目にする日常光景である。
ところが、わが隣の席にあっては異変を目にした。まだ、三、四歳の頃と思える娘もまたすぐに、自分のスマホを片手に動画を見始めたのである。私は驚いて盗み見をした。動画の映像は、人形仕立ての動物の絵柄のようだった。娘の年齢に見合った、とても楽しそうな絵柄の動画である。私は微笑ましく、チラチラと見入った。娘のスマホさばきは、私よりはるかに上手だった。私は、「上手だね」と言って、褒めてやりたかった。しかし、盗み見を両親に咎(とが)められるような気がして、それは止めた。バスが終点の大船へ近づくと娘は、ぴたりと動画を止めて、降りる支度をした。娘の乗車から下車までの一部始終のしぐさは、まさしく「お利口さん」と言えるものだった。同時に私は、わが世(世代)が消えるのを感知し、娘に続いて席を立った。私は世の中の様変わりを感じ、デジタル社会と情操教育の繋がりを浮かべていた。
わが柄でもないことを書いて、年の瀬・冬空の夜が明けている。
垣間見た「お利口さん」の光景
 ひぐらしの記
ひぐらしの記