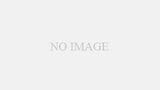互いに老いて、ふうちゃんは身体の病に苦しみ、そして私(しいちゃん)は、精神の傷病(マイナス思考)に苦しんでいる。どちらに手に負えない痛みや苦しみがあるかと言えば、たぶんどっちもどっちであろう。終末人生のもたらす「成れの果(はて)」と思えば、共に腹を立ててもしようがないね。確かにふうちゃんは、まるで「モグラ叩き」さながらにピョコピョコと顕れる病を、彼独特の機知に富んだ表現で打ち負かしている。一方、しいちゃんはそんな才に恵まれず、明けても暮れても愚痴を垂れている。挙句、私は器の違い(小)を曝け出している。だけど私は、才能や器の負けには嘆いていない。すなわちそれは、「竹馬の友」という、名フレーズ(成句)が醸す心地良さに救われているためである。実際には竹馬に乗って、共に遊んだ記憶はない。バカだなあー、成句とはそんな有無など、どうでもいいことである。台無しのことまで書いてしまい、私はつくづく愚か者である。
序章はここで打ち切りにして、さてきょうは、夜長の最長を為す「冬至」(12月21日(土曜日)である。時のめぐりの速さ(感)には、もとより諦念せずにはおれないものがある。だけど、冬至がめぐり来るとそのぶん、短い余生をいっそう削られる思いにとらわれて、痛恨きわまりないものがある。これまたどう鯱(しゃちほこ)だって嘆いても、どうなることでもない。それでも嘆きたくなるのは、これまたわが小器の証しである。
冬至をあすにひかえたきのうのわが家(老夫婦)は、こんな行動をしでかした。それは冬至特有の「ユズ湯」の態勢かためだった。わが家のほったらかしのみすぼらしい柚子の木には、なぜかことしは史上最高と言えるほどにたくさんの実をつけた。きのうの私はそれらの実をもぎ取り、妻はそれらを配り歩く役割に徹したのである。妻は隣近所の6軒をヨタ足で歩いて、5個ずつを配った。どうでもいい行為だけれど、私たちはユズの実に冬至の役割を担わせたのである。確かにこれを終えると、人様のありがた迷惑気分など知ったこっちゃなく、わが夫婦にはきょうの冬至の実感が弥増していたのである。
冬至の夜明けは、満天は日本晴れ、空間および地上にはくまなく、朝日がキラキラと光っている。自然界の恵みにあって、わが満腔(まんこう)には幸せがあふれている。ふうちゃん、まだ、共に頑張ろうね。
冬至
 ひぐらしの記
ひぐらしの記