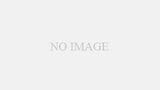12月12日(木曜日)。定時の5時より一時間ほど遅い、起き出しをこうむっている。ゆえに、執筆時間にせっつかれて心が焦っている。しかし、幸いにも夜長の候にさずかり、焦りはいくらか和らいでいる。だけど、ネタとなる得意分野を持たないせいで現在、究極のネタ不足に見舞われている。こんなときはいつもこれまで、ふるさと慕情や母恋慕情にすがり、どうにか文章を繋いできた。ゆえにこれらはわがネタ不足を助けてくれる、あてにならない神様に代わるありがたい助太刀(すけだち)である。
きょうはその片方の母恋慕情にすがり文章を書いて、ネタ不足の難を免れるつもりにある。しかしながら、書き殴りの上にときたま、ふるさと言葉が交じるために読みにくくなり、予(あらかじ)め謝りしておくものである。魚には出世魚と言われものがあり、大きくなるにつけて文字どおり箔をつけてくる。人間でも貴人の場合は、様々な称号が付いてくる。わが子どもの頃にあっての私は、母の呼び名を「母ちゃん」から、「おっかさん」へと変えていた。のちには外面上、「母」一辺倒になった。他人様(ひとさま)一様の母の呼び名は、煌めくことなく「田中井手(たなかいで)の婆さん」一辺倒であった。わが子どもの頃の母は、水車(精米所)の内仕事では、父を凌いでわが家の世帯骨を背負っていた。一方で母は、本来の主婦業ではまるで、独楽鼠のごとく土間に精米機械が据えられていた母屋の内外を走り回り、汗だくの日暮らしに明け暮れていた。
母の主婦業は単品メーカーではなく一手(ひとて)に、まるで今様の総合食品メーカーの役割を果たしていた。蘇る記憶のままに、母の手が作り出す食品類を連ねるとこんなものがある。昼なお暗い味噌小屋に入っては、文字どおり味噌づくりに奔命していた。年の瀬の今頃では、「しのば」(農作業用の別棟の建屋)で、「こるまめ」(納豆)作りに精を出していた。やや時が進むと、正月用の「餅つき」の準備と、当日の主役を担っていた。渋柿が熟れ出す晩秋にあっては、夜なべして「吊るし柿」(干し柿)をこしらえていた。大晦日にあっては、自作の蕎麦から取って蒸したそば粉を平台に置いて、長い捏(く)ね棒で必死に練っていた。正月・元旦と小正月(15日)の雑煮づくりにあっては、またまた避けて通れない母のひとり舞台だった。正月が過ぎて2月になるとこんどは、ひな祭り用の「かきもちや菱形餅づくり」、併せて「くだけだご」(草餅・ヨモギ団子)、5月の節句には「アズキだご」や「ソーダ饅頭」(パン粉で膨らかしたもの)などもこしらえた。「からいもだご」(サツマイモを平たく切って包んだ団子)、「いもだご」(里芋をまるごと包んだ団子)、栗の季節にあっては「栗団子」、まるで百花繚乱さながらの母の手の団子づくりだった。母は、梅の時季には梅干しも作った。これらの合間には、わが好む赤飯蒸かしと牡丹餅づくりを、時をかぎることなくつくり続けた。
総合食品メーカーのみのならず、着物(衣類)の破れているところの縫い合わせ(ふせ)を中心とする裁縫などは、ほとんど夜なべ仕事になっていた。電動の洗濯機や掃除機のない時代の母の掃除は、一仕事とは言えない文字どおり骨の折れる二仕事だった。まだ水道もなく、川水頼りの釜屋(土間の炊事場)仕事、さらには冷蔵庫のない残り物の保存の工夫には、母は全神経を鼓舞しなければならなかった。
書き殴り特有に、きょうもまたいたずらに長い文章になっている。だからここで、書き止めでにするものである。ネタが浮かばないときには、無理して書かないほうがわが身、もちろん人様のためでもある。母恋慕情がかぎりなくつのる半面、草葉の陰の母は声なく、わが勝手ぶりを諫(いさ)めているであろう。私は、胸の透く日本晴れに救われている。
ネタ切れを助ける「母恋慕情」
 ひぐらしの記
ひぐらしの記