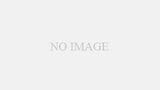現代はストレス社会である。多くの人々は、職場に於ける仕事や同僚との職場環境、家庭での人間関係、老いた親の介護など、いつも精神が休まることのないほどのストレス、つまり医者の治療を必要とする程のゆとりのない精神的緊張に囲まれている。
順調に働いて生活をしていた人が、ある時、うつ病になったり、神経症(ノイローゼ)などいわゆる精神疾患の病気に罹り、通院して薬をもらったりする。場合によっては入院しなければならなくなる。
誰もが、仕事が終った後、すぐに家に帰りテレビを見たり、一時間でも好きな趣味でも楽しみ、その醍醐味を味わったりできれば良い。日曜日はぐっすり眠り体を休め、散歩をしたりして、自由な時間に好きな事に没頭したりして気分転換できれば、心身の健康が維持できる。
しかし、日曜日さえも付き合いで外出せねばならなかったり、場合によっては、その日も出社し、多くのたまった仕事をデスクでやらなければならなかったりする。これでは、仕事などで緊張した精神は休まることがなく、蓄積したストレスは取り除けないばかりか、貯まるばかりである。
ストレスを取り除くための休養(眠ることも含めて)、趣味など好きなことをしたり、散歩やリクレーションなどとして、簡易なスポーツをやるなどをすればよいが、それらをやるためには費用が掛かったり、前述のように仕事に追われ、また家庭の事情によって、趣味などの気晴しに時間を割くことが出来ない場合が多い。
そこで、少しの時間でストレスを取り除き、心の中の緊張を取り除く方法として、箱庭療法がある。
私は一九九七年から九八年に掛けて、神奈川県立高校のいくつもの学校が、自分の学校に勤める教員を講師にして、学校教育以外の内容で特色のある生涯学習として教えるコミュニティー=スクールに参加した。そこで、ある高校で元々は理科の先生であるが、校内でカウンセラーをしている人が教えるカウンセリング入門を受講することになった。
折りたたみ椅子を並べて、数人で行うグループ=カウンセリングであるエンカウンター=グループで、一対一のカウンセリング技法であるロール=プレイング、そして箱庭療法を学んだ。
グループ=カウンセリングは、場所と数人の人数が必要なので、家庭で一人でやれない欠点がある。一対一のカウンセリングは、心の悩みのある人、精神的にノイローゼなどになっている人が受けたいと思っても時間がかかる上、アポイントなどを取り、一対一の対人が必要である。ただし、我々は時によって、知らず知らずのうちにカウンセリングに似たものをやっているのだ。日々の仕事でのストレスで張り詰め圧倒された気持ち、やるせない気分を表現することで吐き出しているのだ。その良い例が、職場の同僚と仕事が終わった後、焼鳥屋や赤ちようちんの酒場へ行き、焼鳥などをかじり酒を飲みながら、仕事の苦言や上役の悪口などを言うことだ。たとえ資格のあるカウンセラーと話しているのでなくても、十分なカウンセリング効果があることを付け加えたい。心の中を話し、上役などの悪口であっても口に出すことによって、気持を和らげているからである。
一対一のカウンセリングやグループ=カウンセリングは、時間と場を設けなければいけないのに比べ箱庭療法の方は、箱庭セットを買えば、仕事の終わった後家へ帰って、十五分から三十分でも、あるいは休日にやればもっと時間があり、実行できるのであるが、一セット二十五万円と高価である上、家庭内に置くことはできるが、白い砂が入っているので、畳の部屋などではこぼしたりするおそれがある。それ故、学校や箱庭療法を治療として実践している病院などの備品や設備として備えるのが望ましい。
このように、箱庭療法を家庭などで好きな時にやるというのは、大変コストが掛かる上、置き場に困るという欠点がある。そこで何か手軽にできるもので、正式な箱庭セットに代わるものはないかと、県立高校でのコミュニティー=スクールのカウンセリング入門講座を終了した後、自宅に於いて工夫、創意、開発を試みた。その結果、三つの箱庭療法代替の行動を編み出した。
一つは箱庭セットの代わりにレゴ=ブロックを使うもの。もう一つは子供が砂場でおもちゃなどを持ち寄り、子供用のシャベルなどで砂を盛り上げたり、小山を作ったりする行動を成人がやる方法、そして最後に、厚紙、とりわけいらなくなったボール紙などをハサミで小さく切り、折り曲げ、そこへ広告などの人や家や木を貼り付け、あるいは、いらない白い紙に色鉛筆やカラー=サインペン、クレヨンで家や木や石、山、自動車、人などどんなものでも描き、ハサミで切り抜き、折り曲げたボール紙のタテの面にノリで貼り付けて、それらを机の上に並べて箱庭の作品、即ち絵模様を作り上げる方法を考案した。
それらを詳細に説明するのは後に回すとして、先ず箱庭療法がいかに考案創造され、心理的、精神的疾患の治療法として確立されたかの歴史を辿ってみる。
箱庭療法の起源は、二十一世紀初めのイギリスに於いてであった。一九一一年にSF作家として有名なH・G・ウェルズが、自分と彼の子供とでおもちゃを床に並べて遊んだ経験に基づき、その体験記を本にして出したところ反響があった。そのタイトルは、「フロア=ゲーム」というもので、それを読んだイギリスのクライン派の小児科医、マーガレット=ローエンフェルド女史が感動し、世界技法(THE WORLD TECHNIQUE)を考案し、子供用の遊技による精神療法として確立した。一九二九年のことであった。
その後、スイスに伝わり、カール=ユング(CARL JUNG)学派のドラ=カルフ(DORA KALFF)によってユング心理学を基盤にし、さらに改良した「砂遊び療法」(SAND THERAPY)が確立され、カール=ユング研究所で科目としてもあり、研究されている。科目では「SAND PICTURE」と呼ばれている。同研究所はスイスのチューリッヒにあり、カール=ユングによって設立され、修了書はいかなる分野でも博士を取った人が、さらに上を学ぶ超博士の学位である。
箱庭療法は、「SAND PLAY THERAPY」とも呼ばれ、心理療法の一種と見なされ、セラピストが見守る部屋の中で、箱の中に自由におもちゃを入れる療法で、心の中にあるものを表現するものと言われている。
箱庭療法は、初めは子供用の心理セラピーとして用いられた。その理由は、未だ学習能力の低い子供や思春期の者達が問題のある自分の心の中を表現するには煩雑すぎるので、つまりそれを言葉で構成して表現するには不向きで、苦手であるが、おもちゃなどで遊技的にすることで自己表現を容易にすることが出来る。それで箱庭は遊技療法として意義があるとされた。現在では子供だけでなく、成人にも精神障害の治療、心理療法に広く使われている。
日本には河合隼雄が一九六一年よりカリフォルニア大学ロサンゼル校(UCLA)大学院に留学中に教わっていた同大教員で、かってヨーロッパから渡って来たユダヤ系ドイツ人カルフに出会い、この時初めて箱庭セットによる箱庭療法を体験した。彼は、かって子供の頃に体験した江戸時代よりある和風「箱庭」に似ていると直感的に思い、その後、カルフの勧めもあってスイスのカール=ユング研究所に留学し、正式に箱庭療法や深層心理について実践体験による研修を積み、一九六五年に日本へ紹介した。河合が勤めていた天理大や、その後の京都大学を中心に広められた。
その後、二人の有能な臨床心理士、山中康裕や岡田康伸によって広められ、大学や学校の心理相談室や病院で精神疾患の治療として普及するようになった。
河合隼雄が留学中にすでに感じていたように、日本には箱庭によく似た和風「箱庭」が存在し、西洋の箱庭療法を受け入れやすい下地があった。江戸時代前からの伝統文化があったようだ。
日本では江戸時代前からお盆に石を載せ、風景を描く盆石、盆山盆景という作品を作る伝統文化があった。その中で木を作る方法で、盆状の植木鉢にミニアチュアーの木を植える作品である。そして、江戸時代の元禄文化の一環で、これらが新しいものとして発展する。
この時期になって箱庭というものが出現する。小さな、あまり深くない箱の中に、小さな人形や橋、船などの景観を構成したミニアチュアーを作り、庭園や名勝などで、絵画的な光景を模型で楽しむものである。明治時代になっても、さらに箱庭は工夫され、類似したものとして盆景を改良した盆栽が出現した。枯山水は逆に大きくしたものだ。
これらの和風箱庭や盆栽、盆景などは、どちらかと言うと年寄りじみた趣味とされていたが、前述のように河合隼雄がヨーロッパの箱庭療法と和風箱庭に共通性があると感じて、箱庭療法を日本に紹介してから、和風箱庭も注目された。
そこで話を転換して、かってコミュニティー=スクールで習得した箱庭をいかに私自身で発展させたか、箱庭を改良したかの本題について述べようと思う。
前にも言った通り、箱庭はカウンセリングやフロイトの自由連想法など、他の心理療法に比べ、少しの時間と本人以外の人が立ち合わなくても、箱庭セットがあれば家庭でも出来る。(但し、通常、学校のカウンセリング相談室や病院などで治療としてやる場合は、本人が箱庭を作る過程で絵模様を作る小さな人や木、家などの順番を心理分析のために医師や第三者が立ち合い確認する場合が通常だが、一人でやっても心を和らげる効果は充分にある。)
箱庭セットは新品で二十五万円ぐらいし、また、家庭だと箱庭セットの箱が大きく、置きづらいことと、砂をひっくり返してしまうので、箱庭セットは通常、学校のカウンセリング=ルームや病院の臨床治療に設備として使うのが望ましい。私はこの箱庭セットを家庭でやるための方法として、子供がやるような砂場で、人が中に入っておもちゃを置く方法を考案した。
その砂場でおもちゃを並べてやる方法は、箱庭セットのもので箱の中に景観を作ることとほぼ同じであることがわかる。大きな違いは、箱庭療法セットは小さな箱の中の砂の上に小さな人、動物、木、家、橋などのミニチュアーのものを箱庭の外側から並べて、絵模様や景観で自分の心の中を表現するが、砂場でやる箱庭は、人と同じ大きさというか、自分自身が砂場という数メートル四方の長方形の大きな箱の中に入り込んで、持ち寄った数々のおもちゃなどを並べて行う、スケールの大きい箱庭療法である。言わば、箱庭の世界に自分も身を置いてやるところに、箱庭セットと心理的に効果が違うように思われる。箱庭セットよりも多くの種類のおもちゃを広い砂場に持ち込め、また砂に起伏を作るにしても、スケールの大きなものを作ることが出来るので、心理的に幅広く表現出来よう。
それらを考慮して、代替できるであろう箱庭療法に類似したものを考案し実践してみた。
その一つが、実際に五歳ぐらいまでの子供が砂場でやっている遊びで、それを子供だけでなく成人(もちろん少年や青年で心の悩みを持っている人も、そうでない人も、ただ遊びという人も含め)がやる方法である。
家の近くの公園や小学校の砂場などで、日曜日など小さな子供が自動車やその他のおもちゃを家から持って来て、そこに並べて遊んでいるのを、誰でも見かけたことはあると思う。子供はおもちゃを並べて、小さなシャベルを使って山を作ったり、砂に起伏を作ったりしている。そして、出来上がると満足そうな笑いを浮かべている。
かって県立高校のコミュニティー=スクールでは、箱庭セット以外にもどんなおもちゃでも使用できることを習った。駄菓子屋で売っている怪獣の模型、コマ、飛行機、戦車、人形、ヘビ、トカゲのゴムなど、プラモデルの飛行機、観光地のおみやげもの、こけし、おもちゃ屋で売っている人形、自動車などなど。大きさはまちまちであるが、箱庭セットの箱庭に入るものなら何でも良い。これを砂場を作ってやると、もっと色々な物を持ち込める。それこそ、やろうと思ったら、自転車のバイク、自転車、コンビカー、大きな列車のおもちゃ、タイヤ、金槌、サッカーボールや野球のボール、バレーボールの球、ものさし、植木鉢、パイロン、お盆や茶わんなど色々な物を持ち込んだって良い。大きな自転車と人を表すのに人形を使っても良い。大きさが違っても、心の中に思う物を表現するのだから、アンバランスでも良い。
私自身が試みたのは、ほとんどは子供のおもちゃなどを使って砂場で砂を盛り上げ、人や小さなカーミニチュアー、プラモデルの飛行機、人形などを使用した。他人がいらなくなって捨てたおもちゃなどをもらって来て使用し、箱庭作品を砂場で作ってみた。幼い子供が砂場で家から持ってきたおもちゃなど、例えば自動車やピストル、飛行機、ロボットなどを並べ、山を作ったりする遊びと同じであるが、それより成人がやると、もっと多くの物を使い高度な絵模様を作るところに違いがあり、成人の作品として意義がある。
しかし、他人から見ると、成人が子供の遊びをしていると思われやすい。学校の砂場に入って私が箱庭をやっているのを幼児を連れてやって来た若い母親が見て、「どうして子供さんの遊びをやっておられるのですか」と声を掛けられてしまった。私は「箱庭療法の替わりを砂場でやっている」旨を若い母親に説明した。
箱庭療法をストレスを抱える人が家庭で箱庭セットを使ってやるには高価であり、なじまないので、代替箱庭として砂場でやる方法を試みたのだが、欠点は仕事をしている人が自宅に帰って十五分ぐらいでは砂場ではやれないので、週末に時間を充分に取れる時に、砂場で実行するしかないということだ。
高校のコミュニティー=スクールで箱庭療法を習った時、中立的な第三者がおもちゃなどを一つ一つ置く順番を記し、カメラで出来上った箱庭の作品を撮影し写真に残した。それに習って、砂場の中へ入って箱庭をやる場合も、作った作品を写真に撮り、出来れば置いた順番をもメモして置くのがよいと思われる。仕事などのストレスで精神が滅入ったり、精神科の医師に診察を受けたり、カウンセリングを受けたりする際に、有力な診断の根拠になるからである。
砂場という大きな箱庭に人が入り、自分自身で箱庭の世界に入っていくので、深層心理として箱庭セットでやるのと違いがあるだろう。
使うおもちゃは何でも使える。子供のおもちゃ、少女のままごとセット、プラモデル、こけし、グリコのおまけ、駄菓子屋の安価なおもちゃ、何でも良い。それらを買ってもよいが、子供が成長していらなくなったものを貰えると良いと思う。そして、使えるものを家庭の中で捜して使うのも良い。コップやサジなどの食器類などを使うと良い。
次に私が考案した箱庭セットに代わってやる代替箱庭療法として、市販のおもちゃ、レゴ=ブロックを使ってやる方法がある。これもある時、ゴミを捨てに行った時、さんざん子供が遊んでいらなくなった古いレゴ=ブロックがあったので、それを持ち帰って来た。レゴが置かれているのを見た時に、ふと、箱庭を連想し、レゴで箱庭をやってみようと思ったのである。
レゴは出っぱったぼちぼちを凹んだところにタテ、ヨコにはめ込み、色々の形を作り出すもので、西洋から日本に販売されている子供用のおもちゃである。主に幼児が保育園や幼稚園へ通っているぐらいの時に、家で両親に買ってもらうか、場合によっては大きいセットだと、保育園に置いてあり、園児がレゴで遊んでいるケースもある。
レゴの場合、価格により大きなセットから小さなものまでセットが違うので一概には言えないが、小さなサイズだけでは、通常の箱庭セットと比べ、作り出す作品に限りがある。テレビのコマーシャルなどで、大きな広場だとか、駅舎とか庭園を作ったものを見たことがあるが、これはごく価格の高いもので、通常のレゴセットでは作れるものではない。
私自身は、ロンドン橋の変形したもの、簡易な駅舎、角ばった馬、平なトンボを作ってみた。これを写真に撮り、高校のコミュニティー=スクールでのカウンセラーに見せたり、当時、睡眠障害でかかっていた東京都港区にある慈恵会医科大学病院、精神科の教授に見せたりした。
慈恵医大病院の精神科の教授は箱庭療法の専門ではなかったが、大変関心を持ち、私がレゴを使ったことを「箱庭セットが二十五万円もするので、安価で買えるレゴ=ブロック=セットを買い、家庭でも好きな時間に十分ぐらいあれば箱庭に替えて出来る」という理由で説明すると、「大変面白いと思う。これは黒田流の箱庭療法だね」という評価を受けた。そして、私の診察カルテに記し、箱庭療法を実際に行なっている医師に紹介すると共に、後日、詳しいレゴをやるに至った説明、つまり代替箱庭としていかにレゴを使おうと思ったかなどをレポート用紙に書き、レゴでやる箱庭についての説明報告書を担当医を通じて箱庭専門の医師に渡してもらった。やはり、その際に高校のコミュニティー=スクールと同様、担当医の教授から、レゴでやる箱庭でブロックを一つ一つはめる時、どれからやったかの順番を書いておくように言われた。慈恵医大病院では実際に箱庭を治療として行っている。もちろん、健康保険が効く。
後日、私のレポートを根拠に慈恵医大の方で学会発表をしたそうだが、それが一九九七年のことであった。その翌年の九八年にテレビにレゴの会社が、「レゴでやる箱庭」というキャッチ=フレーズでCMを流した。慈恵医大からレゴの会社に伝わったのか、それともレゴの会社の方で偶然、私とは別個に思いついたのかは定かではないが、私の方が先に「レゴでやる箱庭療法」を考察したことは間違いない。
サラリーマンなど世の中でストレスを感じている人は、レゴの安いものを買うか、子供さんが成長してレゴで遊ばなくなった家庭を知っていれば、それを貰い、十五分でも毎日やってみてはいかがだろう。精神的ストレス軽減のためになるので。
第三番目に代替箱庭療法として考えたものは、机の上で細長く切ったボール紙を九十度に折り、その紙のタテに折った部分に、人、家、木、動物、山、池などの物で、広告などにあるそれらの写真をハサミで切ったり、いらない紙に色鉛筆、色サインペンやボールペン、クレヨンなどでかいたものをハサミで切ってノリで貼りつけ、箱庭に置く物を多く作り、自宅にある事務机や食卓に並べ、箱庭療法をやる方法である。
堅い紙として、小学生の図工などで使う目盛りの入った工作用のボール紙を買っても良いが、厚紙、ボール紙は家にも色々な商品の中にある。例えば、和菓子の箱、チョコレートの箱、カレーの箱、レポート用紙や便箋の一番下のボール紙、チョコレートの中の厚紙などを使い、ハサミで幅五〜六センチ、長さ十五〜二十センチの大きさに切って、三分の一を折り曲げ、長くなった方をタテにして机に置く。そこに、前述のように広告を切ったりして作った木、家、動物、魚、駅舎、飛行機など箱庭用の置く物を、前述の折り曲げた厚紙やボール紙の長い方にノリで貼り、それをタテにして三分の一の短い紙片で折り曲げた方を水平にして、机の面につけ立てる。そうすれば、それを使って、机に並べて箱庭を楽しむことが出来る。
家や木などの写真広告は、新聞の折り込み広告で良いが、読み終った新聞や週刊誌の中の広告も白黒であっても使う。食べ物や野菜などは、スーパーの新聞の折り込み広告で間に合う。旅行会社の国内、国外ツアーの色刷りパンフレットを貰って来て切り抜くと、温泉旅館や観光地の風景など美しいものを使用できる。それらを前述の厚紙に貼りつけると美しい物に仕上がる。とりわけ、国外旅行のパンフレットだと西洋やアジアの家、駅、建物、寺院、風景などエキゾチックなものが出来る。
広告にない物、例えば、怪獣、SFロボットなどは、いらない白い紙、例えば、広告のウラやお知らせの紙のウラに、色鉛筆やクレヨンで絵を書き、切り抜いて折り曲げた厚紙に貼っても良い。書くのに手間がかかるが、全部手書きのものを使っても良い。
それらを机に並べてやれば、箱庭療法の代わりになり、充分にその効果はあるが、欠点は箱庭セットのような砂による起伏が出来ないことだ。机以外にも床や畳の上でやっても良いが、日本の臨床心理士の中には、学会で箱庭セットの枠が効果があるとした発表をした人もいる。が、それでも床や畳でやることも良い。心理的に効果があるからだ。もちろん厚紙に広告や絵で書いたものの他に、こけしや小さな人形、おもちゃ、駄菓子屋の怪獣、プラモデルの飛行機など合わせて使っても良い。この方法で箱庭の絵模様の作品を作ったなら、レゴでやる作品同様、写真を撮り、物を置いた順番を記しておき、カウンセリングや精神科の医師の所へ行く時の自己心理分析の資料やデータとして役立てると良い。
その他にもおはじきを紙と一緒に並べて花を作ったり、また、おはじきのみの遊びをしたり、少女がやる「ままごとセット」や「リカちゃん人形のセット」を買ったり、それらでいらなくなったのを貰ったりしてやるのも、別の箱庭代替療法となろう。
現代社会でストレスに悩む人は、私が考案した三つの代替箱庭やおはじき遊びなどを家庭で毎日できなくても、時々、短い時間でも行い、ストレスを取り除くべきだ。そして、三つの代替箱庭によって異った深層心理の発見もあり得る。その他工夫として、粘土で動物、虫、ロボット、木などを作り、その他のおもちゃやボール紙に貼った物と混ぜて使っても良いだろう。さらに折り紙を加えても良い。誰でも知っている鶴やカブトだけでなく、折り紙の折り方を示した本は多くあり、複雑でやや折るのに難しいが、色々なものが折り紙としてある。粘土や折り紙は、個々の動物や花などを作るだけでも、作業として心理的にストレスを和らげる効果があるが、さらに箱庭の構築物として使えば、二次的効果があろう。
参考文献及び参考資料
神奈川県立川和高校コミュニティー=スクール「カウンセリング入門」プリント資料 CARL JUNG INSTITUTE
CATALOG一九九五年版 ZURICH SWITZERLAND
WEB SITE WIKIPEDIA 「箱庭」「箱庭療法」「CARL JUNG」「河合隼雄」