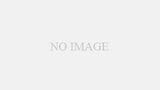1月26日(日曜日)。壁時計の針は6時に近づいている。いまだに夜明け前だけれど、窓ガラスの外に雨はなく、風だけが強く吹いている。しかし、寒気は緩んでいて、身を縮めることはない。確かな足取りで、春の足音が近づいている。寒気に震えていたことを思えばわが寝起きの心境は、気分良く様変わっている。しかしながらこれは自然界の恵みのせいであり、私自身が成し得た好気分ではない。私自身は相も変わらず、こんな心境を携えて起き出している。私自身、妻、総じてわが家の終(しま)い方を案じて、日々心が安らぐことはない。いや、言葉を強めて言えば、日々、終い方の恐ろしさに憂(うれ)えている。もはや私は、日本の国のこの先の行きし方を案じる年齢ではない。わが死んだ先の日本の国は、どうなっても構わないとまでは思うはない。けれど、それに近い思いはある。このことでいくつか、寝起きの心中に浮かべていたものがある。真っ先の一つはこのことである。現下の日本社会には日本政府の施策もあって、「インバウンド」(訪日外国人観光・旅行客)が矢鱈と増えている。この先には、なおいっそう増え続けると予測されている。観光の見所やそれを外国人が愛(め)でてくれることには、日本人として私にも素直に喜ぶところはある。しかしながら一方、外国人が日本の国に定住することとなると、私はにわかに日本の国を行く末を案じて憂えている。昭和の人間・やはり私は、令和の世にあっては、料簡(了簡、了見)が狭いのであろうか。このことでは超絶な思い、すなわちかつての「鎖国時代」さえ偲ばれてくる。これに加えて、この先の日本の国を案じることにはやはり、「少子高齢化社会」と「格差社会」がある。老い先短い私がこんなことを慮って案じ憂えることは、確かに愚の骨頂である。なぜなら、翻ってわが身の周りには、嘆き危惧することが溢れている。それでも真っ先に日本の国の行く末を案ずるのは、長く住んでいることに報(むく)いる老婆心(ろうばしん)の発露であろう。杞憂(きゆう)にすぎないことを願うのみである。満天、日本晴れの朝が訪れている。
日本の国に報いる老婆心
 掲示板
掲示板