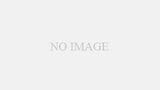起き出して来てパソコンを起ち上げると、デジタル時刻は、4:57と刻まれている。起き出し時刻は、みずから決めている定時(5時)近くにある。まずは生きて起き出していることに、みずからを褒めている。これに微笑(ほほえみ)がともなうと、起き出しは100点満点である。けれど、無念にも笑みは零(こぼ)れていない。いや、笑みの無いことには、ホッとしている。なぜなら、こんなことに笑みが零れたら、もはや私は気狂い(症状)である。パソコン起ち上げの倣(なら)いにしたがって、机上カレンダーを見詰めた。すると、きょう(1月15日・水曜日)には「小正月」と記されている。ふるさと時代の子どもの頃の小正月には、元旦の行事(雑煮餅、神棚参りなど)がそっくり繰り返された。加えて小正月特有に、村中の地区ごとには「どんど焼き」が行われた。村人総出の楽しいひととき(行事)であり、老若男女(ろうにゃくなんにょ)だれもが満面に笑みを湛えていた。青竹の先っぽに差した餅を焼くときには、隣の人の焼け具合を見て呵々大笑(かかたいしょう)の渦が湧いた。さて、きのうは文章を書いている最中に突然、胸の痛みをおぼえて、心筋梗塞を恐れてすぐに文章を閉じた。こののちは幸いにも事無きを得て、明けて現在は、文章書きにありついている。(なんだったんだろう?…)、今ではちょっぴり笑いたくなるような出来事だったけれど、もちろん笑えない。このときの異変に対し、心優しい高橋弘樹様は早速、いつものエールに加えて、貴重なアドバイスを授けてくださったのである。それは、わが日常生活における「笑いのすすめ、笑いの大事さ」だった。数々の笑いの種のアドバイスにあって、究極はこれだった。高橋様の訓えの根幹はこれである。「笑いたくなくても、『はははははーー!!』」と声に出して笑ってみる」。すなわち、笑いの大事さの諭(さと)しである。すると、このことにちなんで私は、スマホを片手にして「笑い」の検索を試みた。このあとは、スマホの記事のそのままの引用である。【笑いとは、楽しさや嬉しさ、おかしさなどの感情を表現する行動です。声や顔の表情で表され、感情体験と深くかかわっています。笑いの効果には、次のようなものがあります。・心身の健康を改善する・免疫力を高める・脳の働きを活性化させる・血行を促進させる・自律神経のバランスを整える・痛みを和らげる・記憶力を高める・認知症の予防に効果的】。「笑いは、感情ではなく行動なので、意識的に増やすことができます。人付き合いを増やしたり、笑いヨガを行ったりすることで笑いを増やすことができます」。きょうは歯医者通い、泣くことは容易(たやす)いけれど、わが日常生活にあって笑いは、とうに消えている。少しは高橋様のアドバイスに報いたいものである。もちろん、わが健康のためである。きのうの突然の胸の痛みは、笑いを忘れているわが日常生活の祟りであったろう。夜明けの空は、どんより曇っている。
知恵者、高橋弘樹様からさずかった教訓
 掲示板
掲示板